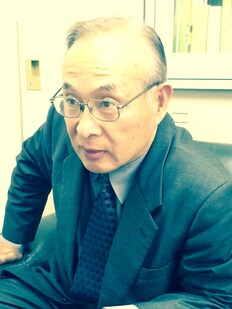基礎控除の引き下げに伴う対象者の拡大、そして最高税率が55%に引き上げ――相続税の大増税時代において、最も大きな影響を受けるのは、いわゆる「土地持ち」の人々だろう。特に都市近郊部の土地は高く評価され、高額の相続税が課されるケースも少なくない。相続税は現金納付が原則だが、資産が不動産に偏っている人(残念ながら日本人資産家の多くはそうだ)の場合であれば、納税資金に窮するケースすら出てくる。不動産は相続人間での分割も難しく、また相続税対策のために購入したアパートが「負の遺産」になっているなど、相続×不動産に関する悩みは枚挙に暇がない。本特集では、それらを解決する様々なアイデア、テクニック、具体的な手法等を紹介する。
■不動産相続の手続きの手順と方法
亡くなった人が土地や建物を所有していた場合、相続人は不動産の相続登記をします。相続登記とは、正確には相続による所有権移転登記のことです。相続登記の方法は、遺言書が残されているかどうかによって異なります。遺言書が残されている場合には、遺言書に沿って相続人を決めますが、遺言書がない場合は、相続人全員での協議によって、あるいは法定相続分で按分します。
ここでは、相続登記の3つの方法についての概要と手続きの手順について紹介します。
■遺言による相続登記
亡くなった人が遺言書を残していた場合は、原則としてその遺言書に沿って相続人を決定します。遺言書による相続登記は、後述する他の方法よりも優先されます。遺言書には、不動産の所在などの情報と、誰に相続させたいかの意思が記されているはずです。遺言書の内容に基づいて、不動産を相続することになった人が不動産の所有権移転登記を行います。
なお、遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人役場で証人の立会いのもと作成されるため法的に有効なものとなりますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、要式に反して作成されていたり、内容そのものに不備があったりして、無効になる場合もあります。例えば「不動産は長男に相続させる」と書いてあったとしても、どの不動産か特定できない場合もあるからです。また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続手続きの前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
■遺産分割による相続登記
遺言書が残されていない場合、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決定することができます。相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言い、決定事項をまとめ、相続人全員の署名、実印の押印がなされた書面を遺産分割協議書と言います。協議の結果、不動産を相続することになった人が所有権移転登記を行います。遺産分割協議による不動産の分割方法は以下の3つがあります。
◇現物分割
現物分割とは、財産ごとに取得する人を決めて分割する方法です。例えば、不動産が2つある場合、土地Aは長男、土地Bは次男というように、不動産ごとに相続人を決めます。この場合は、不動産を評価する必要がなく、不動産を現状のまま相続するので手続きは比較的簡単です。しかし、複数所有する不動産の価値はそれぞれ異なるので、公平性に欠ける場合もあります。現物分割の場合は、不動産を取得した人がそれぞれ所有権移転登記をする必要があります。
■代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、代わりに自分の財産を他の相続人に支払うという方法です。例えば、相続人が兄弟2人だけの場合、5000万円の不動産を長男が相続し、その代わり弟に2500万円を支払うといった具合です。この方法は公平に分割できるというメリットがありますが、不動産の相続人に代償金を支払う資力が必要です。また、不動産の価値を評価する必要があるため、手間がかかるというデメリットもあります。代償分割の場合は、実際に不動産を取得した人が、所有権移転登記をする必要があります。
◇換価分割
換価分割とは、不動産の一部あるいは全部を売却して、その代金を相続人で分割するという方法です。誰も不動産を取得したがらない場合などに向いている方法です。例えば兄弟2人が相続人として、不動産を5000万円で売却し、長男次男がそれぞれ2500万円ずつ相続することで公平に分割することができます。換価分割の場合は、一旦相続人全員の共有名義で登記をする必要があります。
■法定相続
遺言による相続分の指定がない場合は、民法で定められている法定相続分に沿って遺産を分割することができます。例えば、相続人が配偶者、実子2人の場合は、配偶者2分の1、実子4分の1ずつと割合が定められています。不動産を法定相続分で相続するということは、その不動産を共同所有するということです。法定相続の場合は、その後の管理が面倒になるというデメリットがあります。不動産を誰かに貸したいと思った場合や、売りたいと思った場合も所有者全員の同意と押印が必要になります。
さらに、相続した人の誰かが亡くなった場合、その人の持分は相続によってさらに細分化されてしまいます。そうなると関係する人が増え、権利関係も複雑になるため、不動産を活用することがますます難しくなってしまいます。そのため、不動産を共同所有にすることはあまりおすすめできません。
もし法定相続で申請する場合は、登記申請書の相続人の欄に、それぞれの住所、氏名、捺印に加え、持分も記入する必要があります。
■相続登記の必要書類
どの相続方法でも共通で必要となる書類は以下の通りです。
- ・相続の対象となる不動産の登記簿謄本
- ・被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
- ・被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
- ・相続人(相続する人)の戸籍謄本
- ・相続人(相続する人)の住民票
また、遺言による相続登記の場合は遺言書、遺産分割協議による相続登記の場合は遺産分割協議書の提出も必要です。さらに、専門家に手続きを依頼する場合は委任状の提出も必要です。 それ以外にも、被相続人との関係を示すための相続関係説明図、登録免許税の計算のための固定資産評価証明書が必要な場合もあります。司法書士など専門家に依頼すれば、必要書類の取得も代行してもらうことができますが、個人で手続きを行う場合は、必要書類について事前に法務局に確認しておくといいでしょう。
不動産の相続登記は、遺言書が残されているかどうかによって手続きに違いがあります。また、遺言書がない場合の不動産相続にはいくつかの方法がありますので、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことは大切です。 相続登記の手続きは個人で行うこともできますが、不備があって受理されない場合もあります。そのため、司法書士などの専門家に依頼することも検討するといいでしょう。登記をしないままでも罰則はありませんが、後々トラブルの原因となりますので、できるだけ早く手続きを済ませるようにしましょう。
人気記事ランキング


「老後ぐらい贅沢したっていいよね?」貯蓄6,000万円の元会社員が〈ビジネスクラス旅行〉を楽しんだ末、“7年後に直面した現実”

「大学まで出してやったんだから」…年金月6万円・66歳母、上場企業勤務の娘に〈月13万円〉の仕送り要求。“元旦のLINE”で娘が下した決断

「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

じゃあお父さんが黒豆煮たら?38歳娘の一言で揺らいだ「年金25万円」70代夫婦の〈手作り信仰〉…おせち3万円の修羅場

嫁「もうあなたとは他人なんで」と言い残し娘と海外留学…ひとり日本に残された「70代義母」がいずれ知る衝撃事実

いい加減にしろ!…年金月38万円、69歳元教師の父の怒号に静まり返るリビング。実家に帰省した40歳シングルマザーが「父の激怒」に感謝したワケ【CFPの助言】

「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

「月収22万円・東京で頑張る23歳長男」が心配で…東北新幹線でわざわざ上京の「53歳母」、息子が住むアパートをこっそり訪問。そこで目にした「驚愕の光景」

後悔しています…パート先で不倫の末離婚→優しい夫から「現金1,000万円」と「自宅」を奪い取った55歳女性の末路【CFPが警告】

老後資金なんて貯めなきゃよかった…〈年金26万円・貯金3,800万円〉60代夫婦の悔恨。シニアツアーを楽しみ、4人の孫に囲まれ、幸せなセカンドライフのはずが“ため息が止まらない”理由

「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

資産1億円・富裕層突入の43歳会社員。「一生困らない資産」を持ちながら築37年「家賃7万円」木造アパートで暮らし続けるワケ

定年退職日、職場でもらった花束を抱えて帰宅した60歳夫――翌朝、妻の「今日からお昼ごはん担当よろしくね」で始まった“予想外の生活”

「孫はかわいい。でもね…」年金20万円・貯蓄3,500万円の67歳女性が“毎週来る息子一家”に感じる〈正直すぎる本音〉
メルマガ会員登録者の
ご案内
メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。
メルマガ登録- 01/07 高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル… 2026年「日本経済と株式市場」の展望
- 01/08 【地主の資産防衛戦略】 「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み… 権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
- 01/08 金融資産1億円以上の方のための 「本来あるべき資産運用」
- 01/11 <令和8年度>「税制改正大綱」最速解説
- 01/11 2026年「コモディティ」投資戦略 インフレは後退するのか…“金(ゴールド)”“原油”相場を 楽天証券経済研究所のコモディティアナリストが解説
- 01/11 <地主の相続対策> 急な相続で困らないための「資産見える化」のススメ
- 01/11 土地に稼いでもらう! 「借地権」を活用した資産運用と法的問題点 【弁護士が解説】
- 01/11 「タックスヘイブン」を使って、節税・秘匿性確保はできるのか? 「海外法人」の設立法・活用法
- 01/11 “相続の困りごと”いつ誰に何を依頼するべき? 弁護士・税理士・司法書士・金融機関・不動産業者etc. 各専門家の得意なことを知ったうえで考える「適切な専門家・士業の選び方」
- 01/11 相続税の「税務調査」の実態と対処方法 ―税務調査を録音することはできるか?
- 会員向けセミナーの一覧