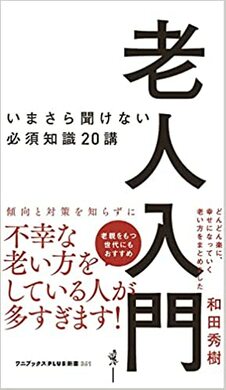超高齢化社会なのにジジババがいない?
■老人の影が薄くなっていないだろうか
いまの時代は超高齢社会だの長寿の時代だのと言われていますが、その割に私たちは老人を身近な存在と感じなくなってはいないでしょうか?
たとえばかつては「おばあちゃん子」という言い方がありました。
忙しい母親にあまり可愛がってもらえない子どもが、おばあちゃんに甘えます。
おばあちゃんは孫をとにかく可愛がります。欲しがるものはできる限り与えようとするし、あまり叱ることもありません。だから子どももおばあちゃんが大好きですし、ときには母親よりおばあちゃんの言うことを聞くようになってしまいます。
「おじいちゃん子」という言葉もあったはずです。それくらい子どもたちにとっておばあちゃんとかおじいちゃんというのは身近で親しい存在でした。
でも年齢を思い浮かべてみると、孫を可愛がるおじいちゃんやおばあちゃんはまだまだ若かったはずです。たとえば子どもが5歳なら両親はせいぜい30代ということになります。昔は若くして子どもを産みましたからおじいちゃんおばあちゃんもまだ50代か60代です。いまの時代に当てはめれば全然、老人ではありません。
しかし子どもはその家の中で少しずつ成長してやがて成人して家を出るときが来ます。それが20歳だとすればおじいちゃん、おばあちゃんも60代後半から70代になっています。
日本人の平均寿命は戦後になって一気に伸びましたが、じつは1970年代でしたら男性がやっと70歳、女性でも70代後半でしたから、孫が20歳になるころは亡くなるおじいちゃん、おばあちゃんがふつうにいたはずです。たとえ20歳が近づいても、孫にとっておじいちゃんやおばあちゃんはやさしくて愛すべき存在のままでした。幼いころは甘えてばかりでも、だんだんいたわるようになってきます。
何を言いたいのかというと、まだ超高齢社会や長寿の時代には程遠かったころのほうが、家庭の中で老人を間近に見つめる時間が長かったし、それだけ人間の老いとか死が身近な出来事だったということです。
いまはどうでしょうか?
おじいちゃんやおばあちゃんのお葬式に出ることはあっても、ほとんどの場合、一緒に暮らした時間がないのですから、老いて死んでいくという当たり前のプロセスに身近に接することがありません。
高齢者がどんなに増えても、その高齢者と接する機会が減ってきたという不思議な現象が起きているのです。