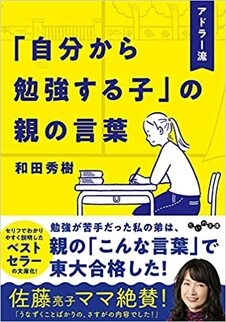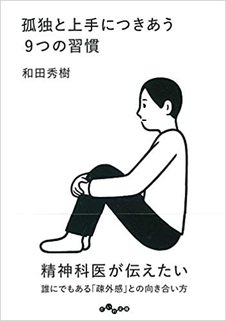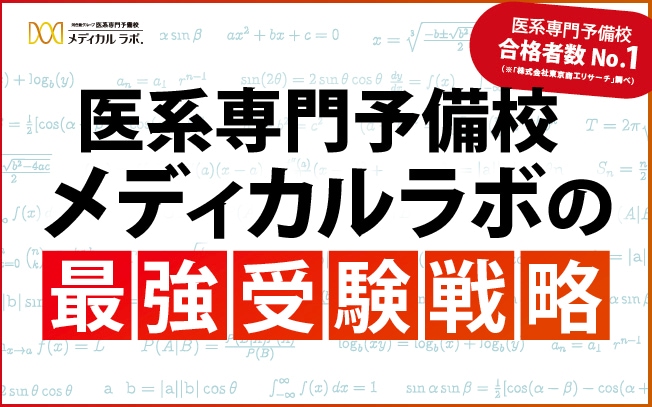【関連記事】灘高2年、下から50番目で東大医学部に現役合格できる理由
子どもの競争心を育む、こんな一言
■友だちにも勉強を教えてあげるといいよ
受験というと、どうしても1人でも多くのライバルを蹴落として勝ち抜く、足を引っ張り合うというイメージが強いようです。
しかし、実際にそのようなメンタリティを持つと、お互いに排除し合ったり、勉強させないように努力したりする方向に向かいます。結果的に、まわりの人だけでなく自分自身の学力を下げることになります。これは芥川龍之介の『蜘蛛の糸』の話を連想させます。
実は、お互いに受験の情報を交換し合ったり、勉強を教え合ったり、ノートを貸し借りしている学校のほうが、受験の合格率が高い傾向があります。
私が在学していた灘高がまさにそうでした。
灘高には、同級生同士で協力して一緒に学力を高めていこうという校風がありました。当時は東大合格者数日本一を争っていたので、助け合いをして、他の学校に負けたくないという気持ちがそれぞれの生徒たちのなかにありました。
受験の勝者は人情味に薄い、人間性が欠落しているというのは間違っています。むしろ受験勝者のほうが人付き合いに優れた子が多いものです。
受験というストレスに打ち勝つうえで、支え合える友だちがたくさんいることは大きな強みとなります。同じストレスを抱える者同士で、共感し合いながら励ましていくことができるからです。つまりストレスの軽減につながるのです。
支え合いながら勉強する経験を通じて、子どもは人間的にも大きく成長することができます。
アドラーの「共同体感覚」は、この助け合いの精神に通じています。みんなで助け合うことでよい社会になる、他人に貢献したことは必ず自分に返ってくるということです。要するにアドラーは「みんなで幸せになる」社会のあり方を提案したのです。
受験を通じて子どもを成長させていくには、親としてのサポートが不可欠です。友だち同士、ときに競い合い、ともに助け合いながら一緒に合格できることがよいことだと教えていきましょう。
子どもは競争と協調が両立することを確実に学んでいくに違いありません。