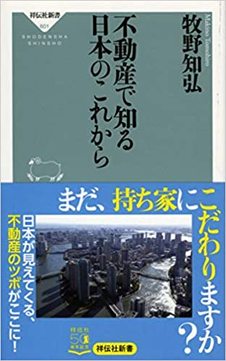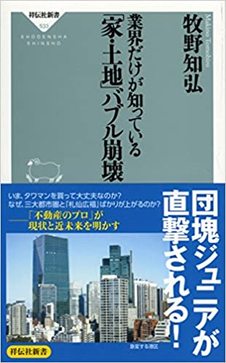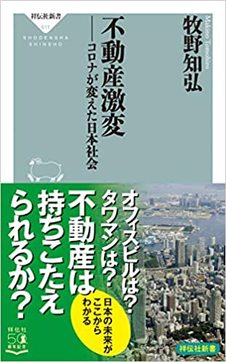いい大学、いい会社=人生の成功パターン
企業という村に毎日通勤して、村の中の論理だけで働き、報酬を得る。これがあたりまえだったときには、働くということはそれほど難しいものではありませんでした。働くことの意味合いの多くが、組織の一員であるという安定的な基盤の上に成り立っているからです。
働く場所が基盤であるならば、その基盤はなるべく大きく強固なもののほうがよい。それはすなわち、大企業であるほど安心であるという理屈になります。就活をしている大学生の思考パターンは、まさにここにあります。

日本ではいつの頃からか良い家に生まれて、多額の教育費を惜しげもなく注ぎ込まれて良い学校に入り、良い会社であるはずの大企業に無事就職をするというのが、人生の成功パターンになっています。これはある意味エリート層の再生産をやっているようなものです。この循環が長期にわたることになれば、社会には新たな階級が生まれ、格差はどんどん拡大していくことでしょう。
現在では、たとえば政治の世界でそうした弊害が指摘されています。先代の地盤を引き継いだだけの二世あるいは三世議員ばかりが国会を占め、民の本当の傷みや苦しみを理解できない、しようともしない政治に失望している人もいます。
実は、大企業社会の中でも同じような閉塞感が出始めています。二世や三世社員が増えたというわけではありません。同じような思考回路を持つ金太郎飴のような社員ばかりで組織が構成されるようになってしまっているのです。あたりまえです。これまでの学校教育では、言われたことを素直にやる子が高く評価されてきたからです。
特にテストでの成績偏重を改め、内申書を重視するようになってからはこの傾向がひどくなったように感じます。以前は先生に逆らうヤンチャな一面を持っている子でも、テストの成績が良いと一定の評価がなされました。ところが、今はある程度内申書の評価を高めないと学校では評価されにくい仕組みとなっています。