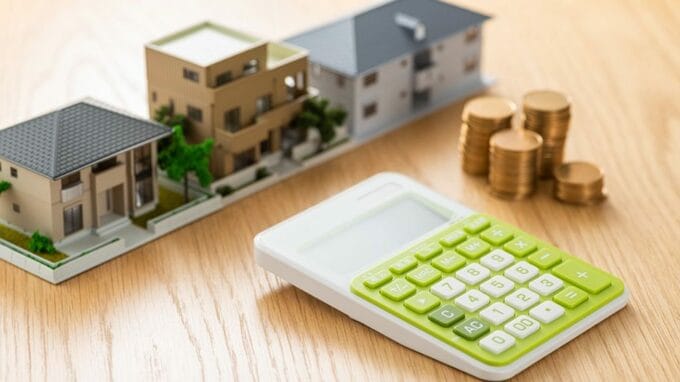土地建物の区分がわからず、消費税額が不明瞭なときの対処法
なかには合計の金額しか把握しておらず、契約書に「消費税額」が記載されていないこともあります。そうした場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
法令等
消費税法には、合理的に区分されていない場合には、譲渡時の価額である時価により按分すると規定されています。そのうえで、国税庁のタックスアンサーでは以下の方法などにより合理的に区分するとしています。
1. 譲渡時の時価の比率による按分
2. 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3. 原価を基にした按分
さらには、国税庁の質疑応答事例には不動産鑑定評価が合理的であると認められるときは鑑定評価額により取り扱ってよいことが掲載されています。
これらより、消費税法では時価による按分を基本的な考え方として、そのなかで合理的に区分する方法として、固定資産税評価額等による按分や不動産鑑定評価が挙げられています。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引き、納付するという仕組みになっていることを考えると、当事者間で合意した建物の金額に基づき申告すれば問題はないように感じます。しかし、非課税取引である土地の譲渡が一緒に生じることもあり、そう単純にはいきません。売買契約書に記載された建物と土地の金額に基づき消費税を計算する場合であっても、合理的に区分されている必要があります。
なお、譲渡所得の特別控除に関する措置法通達には、一括取得した場合の取得価額の区分については以下によると記載されています。
1. 契約において区分され、取得時の価額である時価としておおむね適正なものであるときは、契約により明らかにされている価額
2. 建設業者から取得した場合には、建設業者の帳簿書類に記載されている価額
3. 取得時の価額である時価の比率により按分して計算した価額
消費税法の通達には、所得税、法人税の特例計算における取扱いにより、区分しているときはその区分よると記載されており、特例計算により区分していないときまで、措置法通達は適用されないことになります。参考にする場合でも、時価としておおむね適正なものであるという前提条件が付いており、時価で按分するという基本的なスタンスに変わりはありません。
裁決・判例等
不動産の一括譲渡、取得に係る判例や裁決は多くあります。以下は、国税庁や国税不服審判所のホームページに掲載されている判例や裁決であり、誰でも見ることができます。

各判例をいくつか見ていきましょう。
①契約書に記載された建物の金額で算定することが相当であるとされた事例
(国税不服審判所、H20.5.8裁決、裁決事例集No.75)
納税者が行った固定資産税評価に基づく法人税申告に対し、税務署が売買契約書金額を評価金額とすべきであると更正処分を行いました。その処分を納税者は不服とし、取り消しを求めた事案です。
このケースでは、売買契約書の建物の金額を不動産売買の仲介業者の査定額を参考にして決めており、ほかに同族会社等の特殊な利害関係、租税回避の意思や脱税目的が認められなかったため、税務署の更正処分が正当であると判断されています。
④不動産鑑定評価の比率による按分が合理的であるとされた事例
(東京地裁、R4.6.7判決)
商業地域にあるテナントビルの売却価額の按分方法について争われた消費税の事案です。税務署が固定資産税評価額の比率により更正処分を行ったものの、納税者の申出により裁判所の選任した不動産鑑定士が収益還元法による鑑定評価を行いました。裁判所は当該評価の一部を補正したものの、資産の個別事情を考慮した適正な鑑定として不動産鑑定評価が合理的であるとし、納税者の主張を全面的に認める判断をしました。
⑤固定資産税評価額により按分すべきとされた事例
(国税不服審判所、R4.9.9裁決、裁決事例集No.128)
納税者が契約書に基づき按分して所得税申告を行いましたが、税務署は固定資産税評価額に基づき按分すべきとして更正処分を行いました。その処分を不服とし、取り消しを求めた事案です 。
契約書に記載された建物の金額が、その固定資産税評価額を大きく上回っているにもかかわらず、土地の金額はその固定資産税評価額と同様かまたは下回っていることから、客観的な価値として著しく不合理であり、税務署の更正処分が正当であると判断されています。
ここまで、 契約書、不動産鑑定評価、固定資産税評価が採用された事例を紹介しましたが、これまでの判例等を見ると、処分庁である税務署は固定資産税評価額に基づき按分しており、審判所もそれを支持している傾向がうかがえます。