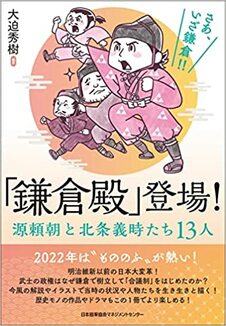【関連記事】北条政子が頼朝の元へ…この駆け落ち婚が源頼朝を「鎌倉殿」に
「鎌倉殿」は武家政権の基盤づくりで
■浮気モン「鎌倉殿」
治承・寿永の乱(源平合戦)の滑り出しはまずまずでした。
しかし、富士川の戦いのあと、頼朝は東国ボスたちの説得を聞き入れ、いったん上洛をあきらめます。東国の平定を優先し、1180年末から鎌倉で、新しい武家政権の基盤づくりに取りかかったのでした。
年が明けてまもなく、頼朝のもとに“吉報”がもたらされます。清盛病没の知らせでした。64歳での死去。高熱にうなされながら発した清盛末期の言葉は〈わしの墓前に頼朝の首を供えよ……〉だったと伝えられます。
すぐさま後白河法皇は院政を再スタートさせましたが、政権を掌握していたのは平氏でした。トップは清盛の子・宗盛。天皇の座にあったのも、清盛の孫・安徳天皇でした。
養和元年の1181年は、清盛の祟というわけではないでしょうが、天候不順が続く不穏な年でした。全国的な飢饉に見舞われ、都でも大量の餓死者が出たのです。その惨状は、鴨長明が『方丈記』に詳しく記しています。朝廷内の政権争いも、いったん休止せざるを得なかったほどでした。
このころ、「鎌倉殿」は何をしていたのでしょう?
武士政権の基盤づくり、鎌倉の都市づくりに励みながら、また、子づくりにも励んでいました。いずれも順調で、政子のお腹には2代目「鎌倉殿」になる予定の頼家が宿ったのです。
しかし、相変わらず浮気にも励み、「亀の前事件」を引き起こしてしまうのでした。
もちろん、女性のことばかりを考えていたわけではありません。頼朝は、御家人の「殿」です。東国のリーダーとしてどうすべきか、平氏政権とは違う、新しい武士政権をつくるには何をすべきか、常に模索していたのです。
本当にザンネンだったのは、そうした兄の真意や展望が弟・義経に伝わっていなかったことかもしれません。いったい、どういうことでしょうか?
頼朝は懲りない男でした。鎌倉に拠点を置いた2年後の1182年。頼朝はふたり目を身ごもった政子の眼を盗み、亀の前という美女と逢瀬を重ねたのです。これに政子の怒りが爆発! すぐさま近臣の牧まき宗親に命じ、逢瀬の館を破壊させたのでした。
ところが頼朝は、破壊実行人・宗親に対し、〈先にオレに知らせろよ!〉と逆ギレ。宗親の髻(まげ)を切ったのです。武士にとっての恥辱。宗親は、時政が溺愛していた牧の方の父(兄とも)であり、今度は時政が頼朝にブチキれ、一族で伊豆に帰ったのでした。このとき、義時は鎌倉に残ったため、頼朝の信を得たといわれます。