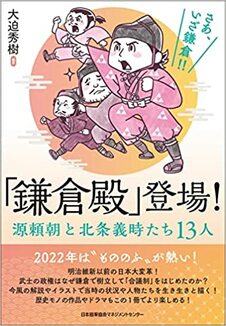後鳥羽上皇の要求に対する幕府の答え
■譲れない! 鎌倉幕府の権利
幕府と朝廷の関係は悪化の一途をたどっていきました。
このあと、中世史のターニングポイント「承久の乱」へと突き進んでいきます。
源頼茂の乱の前、親王下向をめぐる後鳥羽上皇と幕府の交渉過程で、またひと悶着がありました。女性が絡む問題で、これが承久の乱の着火点になったともいわれます。
後鳥羽上皇が幕府に、地頭の罷免を要求したのです。
問題になったのは、摂津国(大阪府)のふたつの荘園の地頭でした。どちらも、後鳥羽上皇が愛妾の亀菊にあたえていた荘園で、上皇は意のままにならぬハエのような地頭を追い払おうとしたのです。
これに幕府はどう対応したのでしょうか?
東国は支配下に入れているものの、西国での幕府の影響力は微々たるものでした。たかが都に近い摂津国の地頭の、いち任免問題にすぎません。
〈この程度のことで、朝廷と衝突するのは愚かしい。ここはひとつ、後鳥羽上皇に恩義を売っておこう!〉
……などとは、北条義時も政子も大江広元も、幕府のだれも考えませんでした。
地頭の任免権は、鎌倉幕府にとって絶対に譲ることのできない権利です。
鎌倉幕府を朝廷から独立した東国の政権(東国国家論)とみるか、朝廷を中心とする国家統治の枠組みの一部門(権門体制論)とみるか、当時の公・武政権の捉え方は大きくふたつに分けられます。
ただ、どちらの見方も、将軍と御家人の揺るぎない関係を否定することはありません。
鎌倉幕府はこれまで繰り返してきたように、「御恩と奉公の主従関係」で成り立っています。御家人は御恩として所領をいただける、すなわち地頭職につけるからこそ、将軍「鎌倉殿」のために命を賭して戦い、奉公するのです。これが鎌倉幕府の存在意義なのです。
当然、後鳥羽上皇の要求に対する幕府の答えは「ノー」でした。