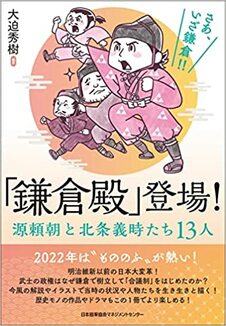【オンライン開催(LIVE配信)】希望日時で対応(平日のみ)
「日本一富裕層に詳しい税理士」による無料個別相談セミナー
富裕層の相続対策から税金対策の悩みを一挙解決!
詳しくはこちら>>>
マルチな後鳥羽上皇と3代目「鎌倉殿」
■多芸多才な後鳥羽上皇
鎌倉で北条政権が確立されつつあったころ、京の朝廷はどんな状態にあったのでしょう?
後鳥羽上皇による院政がしっかり機能していました。上皇は、各地に分散していた皇室領荘園を集約し、財力を蓄えていました。また、新たに西面の武士を置き、都の武士を護衛にあたらせるなど、軍事力も強化していたのです。
そのため、都の御家人は、朝廷と幕府の両方に仕えるという“宙ぶらり”な状態に置かれることになりました。さらに頼朝が亡くなって以来、鎌倉では“仁義なき戦い”が続いていたこともあり、在京の御家人は自分の身の置きどころに迷いが生じていたのです。このことが、のちに幕府を揺るがすことになります。
後鳥羽上皇のこれまでを、少し振り返りましょう。
高倉天皇の第4男として、1180年に生まれました。初代「鎌倉殿」頼朝が挙兵した年です。天皇に即位したのはわずか3歳のとき、源平合戦さなかの1183年です。平氏と安徳天皇の都落ちにともなっての即位でした。
しかし、即位の儀に欠かせない三種の神器はありません。平氏が都から持ち出していたからです。さらに壇ノ浦の戦いで、草薙の剣が海に消えました。
あるべき三種の神器が“欠落”した、異例の即位だったのです。このことが、後鳥羽天皇の生涯に影を落としました。強いコンプレックスになったのです。
しかし、後鳥羽天皇はそれをバネにするように、帝王学を施されながら、さまざまな学芸・武芸も身につけていきました。
1198年、土御門天皇に譲位すると、後鳥羽上皇となって院政をスタートさせました。それまで権謀をめぐらしてきた源通親も抑え込み、だれからも脅かされることのない、「治天の君」として君臨していたのです。
後鳥羽上皇は類稀なマルチな才能の持ち主でもありました。
和歌と蹴鞠という当時の教養だけでなく、音曲(笛や琵琶)、笠懸、相撲、水練(水泳)、囲碁、将棋 ……と、文武から遊戯まであらゆる分野に秀でていたのです。
祖父の後白河法皇も好奇心が旺盛で、多趣味でした。ただ、後白河法皇の好奇の眼が今様や俗謡、白拍び子といった軽めの“サブカル”に向かいがちだったのに対し、後鳥羽上皇はそれらを嗜みつつも、好奇の眼を王道の武芸や学問にもしっかり向けました。
また、朝廷の有職故実の復興にも熱心でした。後鳥羽上皇は伝統的な王朝の復興をめざしていたのです。
この後鳥羽上皇に心酔していたのが、3代目「鎌倉殿」実朝でした。実朝の名付け親が後鳥羽上皇だったことも拍車をかけていました。
後鳥羽上皇は、鍛刀にも強い関心を示しました。腕の立つ刀工を離宮に集め、また自らも刀を打ち鍛えました。その技術はきわめて高く、銘刀「菊御作」を制作しています。ネガティブなコンプレックスこそが、エネルギーの源泉。これも、草薙の剣の“欠落”への反動が生んだ賜物という見方もできるでしょう。
なお、上皇の刀剣が「菊御作」と呼ばれるのは、銘の代わりに上皇自ら「菊の紋章」(菊花紋章)を刻んだからです。これが正式な「皇室の紋章」として、今日まで伝えられています。