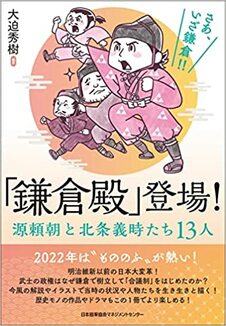【関連記事】北条政子が頼朝の元へ…この駆け落ち婚が源頼朝を「鎌倉殿」に
「鎌倉殿」の許可なく義経の叙任が火種に
■義経の快進撃、それとも暴走?
目ざましい活躍もあった義経の叙任は、東国の支配者である「鎌倉殿」の許可・推挙を得ぬままのものです。朝廷から独立した武家政権を構想していた、あるいは朝廷との程よい距離を模索していた頼朝にとっては、いまいましく、看過できないことだったのです。
頼朝は平氏を壊滅させることより、平氏から三種の神器を取り戻すこと、安徳天皇を無事に京へ帰すことを第一に考えていたとも思われます。そうすれば、法皇からさらに厚い信頼を得て、東国で好き放題できるからです。
一方、義経は平氏を壊滅させようと意気込んでいました。頼朝はそんな血気盛んな義経にストップをかけ、もうひとりの弟・範頼に平氏攻略を命じます。
しかし、範頼は十分な戦果を挙げることができません。戦況は膠着状態に陥り、平氏は讃岐 (香川県)の屋島で勢力を回復しつつありました。法皇も、平氏の動向に戦々恐々としています。
結局、義経に頼らざるを得ない状況となり、頼朝はやむなく、義経に出陣を命じたのです。奮い立った義経は屋島の戦いで、またもや際立った軍事の才を発揮しました。
「西船東馬」という言葉があるように、海の戦いでは西国の平氏が有利でした。平氏は多くの船団を従え、瀬戸内の海を知りつくしていたからです。
海から真正面に屋島を攻撃しても勝てる見込みはありません。そこで義経は、屋島から離れた場所に上陸して陸路から遠回りし、油断していた平氏軍を背後の山から襲ったのです。平氏軍はひとたまりもありませんでした。
■海のもくずと消え……
またもや裏をかかれた平氏は、さらに西へと下っていきました。〈もはやこれまで〉と平氏から源氏に寝返る武士もあいつぎました。
1185年3月、壇ノ浦の戦いで平氏は滅びます。盛者必衰の理――どんなに栄えたものも、いつかは必ず衰えるという仏教の道理は、平氏も例外ではありませんでした。
平氏滅亡の一報は、鎌倉の頼朝のもとに届けられました。しかし、頼朝にとって、諸手を挙げて喜べる朗報とはいえませんでした。頼朝は感概に浸りながらも、少し顔を曇らせたのです。なぜでしょうか?
義経の独断専行が目に余り過ぎたからです。また、三種の神器も天皇も失い、朝廷のもとに帰すことができなかったからです。壇ノ浦の戦いで、三種の神器のひとつ草薙の剣が海に消えました。安徳天皇も祖母の二位尼(平時子、亡清盛の妻)とともに入水したのでした。
このとき、二位尼は6歳の安徳天皇に「波の下にも都がありますよ」と説き促したといわれます。
捕虜の平宗盛らを引き連れ、都に凱旋した義経は鼻高々でした。法皇から新たな官職(院御厩司)をたまわり、京の人々からも大歓迎されました。
〈粗暴な「田舎モン」義仲とはえらい違いだ!〉
〈顔はイマイチだと思ったけど、カッコイイじゃない!〉
平氏壊滅のミッションを完遂した義経は、当然のように兄・頼朝からも笑顔で迎えられると期待に胸を膨らませていました。兄の真意をまだ理解できていなかったのです。
一連の合戦には、梶原景時も同行していました。しかし、義経と景時のあいだでは戦術などをめぐり、ひと悶着もふた悶着もありました。このことが、義経の行く末をさらに険しいものにするのでした。