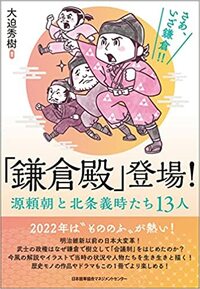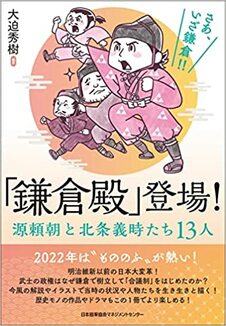義時死後の後始末をして政子が天寿を全う
承久の乱から3年後の1224年、北条義時が没しました。
享年62歳。脚気に急性腸炎が重なっての病死でしたが、伏して間もない死だったので、やはりさまざまな憶測を呼びました。
弟の北条時房、子の泰時は、京の六波羅の館で訃報を受け取りました。ふたりは乱の戦後処理にあたりながら、朝廷に不穏な動きがないか、眼を光らせていたのです。
ふたりとも、すぐ鎌倉に向かいました。義時の葬儀に参列するためだけではなく、鎌倉で義時の後継をめぐり、不穏な動きがあったからです。
なお、六波羅での職務はその後、整備・拡張され、西国の御家人の監視や京の治安維持の任も兼ねた幕府の正式な出先機関になりました。のちに六波羅探題と呼ばれます。六波羅は五条大橋の東一帯の地名で、かつて平氏一族の館が集まっていました。そのため、平氏政権は「六波羅政権」とも呼ばれていました。何かと因縁のある地なのです。
さて、鎌倉で不穏な動きを起こしていたのは、義時の後妻・伊賀の方でした。「尼将軍」政子に不満を抱いていた伊賀の方は、一族で幕府を支配しようと画策していたのです。その相談相手になっていたのは、この手の陰謀説では“常連”の三浦義村でした。
政子の行動はいつも素早く、迷いがありません。義村を問い詰め、伊賀一族を流罪にしました。そして、大江広元ら宿老の承認も得て、北条泰時を3代執権に任命したのです。このとき、泰時は43歳でした。
慈円の『愚管抄』のなかに「女人入眼の日本国」というくだりがあります。慈円は北条政子と藤原兼子を念頭に、〈日本の国の仕上げはいつも女性が行う〉という意味で、この一節を記したのでした。仏像も眼を入れなければ、魂は宿らないということです。
翌1225年7月、日本国に眼を入れたことを確信したのか、北条政子が天寿を全うしました。そのひと月前、大江広元も他界しています。ちなみに、慈円もこの年に往生しています。
ひとつの時代が終わったのです。