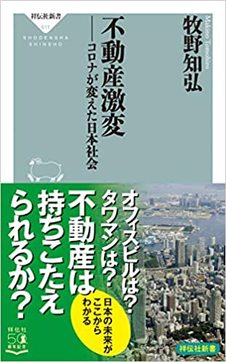オフィスビルの「テナントドミノ」が起こる
オフィスビルマーケットは今後需給バランスが大きく崩れ、空室が増加して賃料が下落するという姿を描いてきました。都心再開発の掛け声のもと、続々と竣工する航空母艦クラスの超巨大オフィスビルは、既存ビルとの間でテナントを求めて壮絶な引き抜き合戦を始めるはずです。
航空母艦ビルに入居するのは、賃料負担力の高い外資系金融機関や国際法律事務所、コンサルティングカンパニーやITソフトウェア系、グローバル企業の一部が対象となるはずですが、バブル崩壊による景気の悪化はこうした産業の業績を下振れさせることにもなります。

賃料を下げ、長期間のフリーレントを設定して、新築ビルは既存大型ビルのテナントの引き抜きを画策します。新築ビルの強みは何といってもその設備仕様の良さです。耐震設計であることはもとより、豪華なロビーエントランス、万全のセキュリティチェック体制、快適な水回り設備、レストランや物販など、充実した館内施設を売り物にテナント誘致を試みます。
引き抜かれた既存大型ビルが向かうのは、自分たちのビルよりも設備仕様が劣る中型ビルのテナントです。これまでは賃料水準が適合しなかったのですが、背に腹は代えられません。特に中型ビルで複数のフロアに跨って入居しているテナントなどには、
「フロアを統合できるので床面積が小さくてすみます」
「フロアを統合することで業務効率も格段に向上します」
などとセールスして移転を勧誘します。
複数フロアで空室になってしまった中型ビルは、仕方がないので小型ビルのテナントに声がけを始めます。フロア全体を借りてくれるようなテナントは小型ビルではなかなか存在しませんが、フロアを間仕切って少しでも穴埋めをしようとします。設備は小型ビルよりはましなので、同じ程度の条件であれば小型ビルのテナントも満足できるはずです。
こうしたビルテナントの移動を私は「テナントドミノ現象」と呼んでいます。よくバブルが崩壊すると新築のオフィスビルがガラガラになると思いがちですが、実際の市場では、当然「弱肉強食」の世界が展開されます。強いものが弱いものに次々と襲い掛かることで、最後に「しわ寄せ」を食らうのが、実は町中の中小ビルオーナーということになります。
中小ビルの多くが日本の経済の発展と軌を一にするように1970年代から80年代の後半にかけて建設されてきました。この頃の東京や大阪、名古屋など大都市圏のオフィスビル市場は、常にテナント需要が旺盛で、賃料は一方的な「右肩上がり」を享受できました。