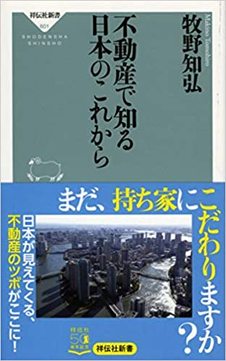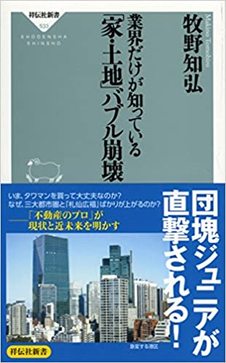かけ声倒れになった「地方創生」のスローガン
日本の地方は戦後から高度成長期、そして平成に至るまで常に「ひと」を都会に供給し続けてきました。
この間、東京への一極集中を改め、地方の人口減少を押しとどめ、国土の均衡ある 発展を目指すという政策は何度も策定されました。かつて田中角栄が自らの著書『日本列島改造論』で唱えたのも、地方経済を豊かにするために全国に高速道路や新幹線を整備していこうというものでした。

しかし、角栄の狙いとは異なり、日本列島中に張り巡らされた新幹線や高速道路は、「ストロー現象」などと呼ばれるように、結局地方から都会に人を「吸い上げる」役目しか果たしませんでした。これらのインフラ施設はすべて、地方から都会に向かう「上り」経済のツールでしかなかったのです。
地方をなんとかしよう、もう一度輝きを取り戻そうという動きは、2014年9月に第二次安倍内閣が発足した時に掲げられた「地方創生」のスローガンにも示されています。
あれから3年以上の時が経過しました。最初に地方創生担当大臣に石破茂さんが就任した頃は、メディアでは、ほぼ毎日のように地方創生の単語を見つけることができましたし、地方創生に取り組む自治体や関係者の姿が頻々に報じられたものです。
ところが最近では地方創生というスローガンは、国会でもメディアでもあたかもど こかに忘れ去られてしまったかのような扱いとなり、いつのまにか「一億総活躍社会」にその名を変え、2017年10月の総選挙後は、「働き方改革」「生産性革命」へと猫の目のように政策が変わる中、地方創生は日陰者扱いになりつつあるというのが現状です。
もともと日本の地方発展の施策は、高度成長期以降、「製造業」中心の経済において、もっぱら工業団地の造成と造成した団地への工場の誘致というステレオタイプなものばかりが繰り返し行なわれてきた、という歴史があります。
地域の産業振興と雇用の確保というのが目的ですが、これらの工場の多くは所詮、大企業を頂点とする巨大なピラミッドの一部に組み込まれていて、一定の雇用が確保できたとしても、その結果として地域自体の文化が育まれ、地域の基盤や根幹となるような振興策ではありませんでした。
加えて、90年代後半以降は、円高を嫌気して多くの工場はアジアにその拠点を移し、自治体はいくら土地を造成して、有利な税制などを拵えて企業を誘致しようにも、反応する企業は少なく、もはやこの方程式がまったく通用しなくなってしまっていることに今、多くの自治体が困惑しています。