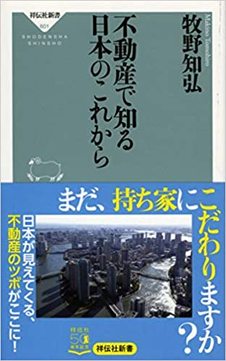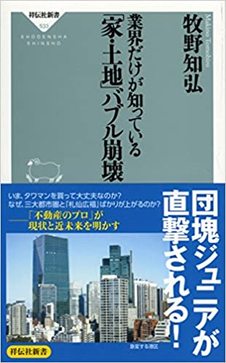ビルオーナーは法人相手の箱貸しビジネス
1995年あたりを境に変わってきたもう一つの現象が、不動産オーナーの懐具合です。不動産オーナーといえば、すぐに思い浮かぶのはアパートオーナーですが、不動産もいろいろ。オフィスビルオーナーもいれば、マンション一棟を所有しているオーナーもいます。サラリーマンが資産運用として所有するワンルームマンションオーナーなどもいます。土地だけを貸地として運用している土地オーナーもいます。
不動産を持って運用、つまり賃貸することのメリットは何でしょうか。当然賃料を収受できることです。昔から不動産大家は、町の「お金持ち」「左団扇で楽々」といったイメージがあります。

それもそのはず、特に首都圏などの大都市圏の郊外では、続々地方から都会にやってくる大量の人々にとっての住宅が、常に払底状態にありました。
たいして不動産に知識がなくとも、余っている農地や遊休地に銀行や不動産屋の言いなりにアパートを建てても、あっという間に満室となり、家賃収入が入ってきます。アパートは学生さんのような若い人が中心なので、卒業したりするとアパートを出ていきます。しかし、また同じように新しい学生さんが入居してきます。
テナントが入れ替わるたびに、礼金などの副収入も入ってくる。家賃も経済の発展とともに上昇していますが、テナントがそのままではなかなか家賃の値上げをするのも面倒くさいです。ところがテナントが入れ替わるのであれば、新しい家賃で入居する、つまり収入はますますアップする。こんな構造にありました。
都心の中小ビルオーナーも儲かりました。それまで八百屋や蕎麦屋を営んでいたような商店も戦後、オフィスエリアが拡大するにつれて商売をやめてオフィスビルに建て替えました。
戦後、事業所の数はどんどん増加を続け、中小オフィスビルはその受け皿としての機能を果たしました。「賃料とは上がるもの」、平成バブル崩壊まで、日本の大都市の賃料は経年とともに「必ず上がる」という素晴らしい環境下にありました。
オフィスビルオーナーはアパートオーナーよりもさらに「楽ちん」な稼業でした。アパート住民は建物内で生活をするので、いろいろなトラブルを起こします。トイレや風呂が詰まった、お湯が出ないなどは序の口、隣人の声がうるさい、ゴミ出しルールが守れない、男女の痴話げんか、家賃の滞納など、オーナーはまるで「人間動物園」の運営者のようです。
一方でビルオーナーは所詮、法人相手のハコ貸しです。夜は基本、帰ってくれるし、テナントが建物内で生活するわけではないので水回りなどのトラブルは少ない。アパートに比べれば法人相手なので賃料などの「とりっぱぐれ」も少ない、など運営は比較的楽なのです。