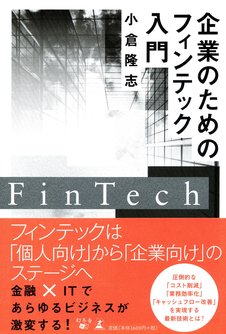建設業のビジネスモデルは「資金繰り」に課題が・・・
POファイナンス®のメリットが特に大きいと思われるのが、建設業です。
日本全国に建設事業者は約46万社あり、その99.4%が中小企業です。建設業は、人件費や建築資材の調達などで先に資金が出ていき、後に発注者から支払いを受けるという、構造的に資金繰りが厳しいビジネスモデルです。建設作業員への支払いは日払いのケースも数多くあり、資金を確保できるかどうかが、経営上非常に重要な課題です。
例えば、中小規模の建設会社が分譲マンションなど大きな案件を受注すると、1件だけで前年の売上高の半分を超えてしまうようなケースもあり、こうした場合は間違いなく運転資金が足りなくなります。
国や自治体が発注する場合は工事費全体の4割を前金として支払う制度がありますが、民間では必ずしもそうはいきません。民間工事の場合、支払いまで約7カ月かかる「台風手形」や、着工時に請負金額の10%、上棟時に10%、竣工時に残りの80%を支払う「テンテンパー(10:10:80)手形」など、支払い条件が非常に厳しいものも見られます。
竣工引き渡し前に「最大5割」の資金提供が可能
しかし、POファイナンス®を使えば、竣工引き渡し前に最大5割の資金が建設業者に提供されるのです。
建設業では、施工能力はしっかりしているものの金融調達能力が弱いという会社がかなりあります。POファイナンス®を利用すれば、そうした建設会社も資金繰りの苦労がなくなり、工事の品質確保や営業に力を入れられるようになるでしょう。
発注側にとっても建設工事を依頼する際、自らの資力、信用力、資金調達力で建設工事における資金繰りをコントロールできるので、トータルで見た金融コストも下がるのではないかと思います。
ところで、このPOファイナンス®の電子記録債権は発注時から発生させるため、期間が下請法の現行規制の120日を上回ることが想定されます。この点については公正取引委員会より、発注から納品までの期間については下請代金ではないとのコメントがありました。
下請法の規制の日数計算に電子記録債権の発生から納品までの期間は算入しませんので、適法に運用できます。