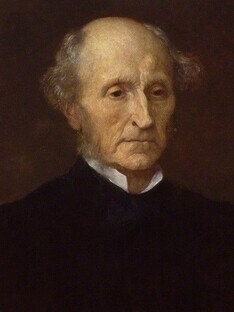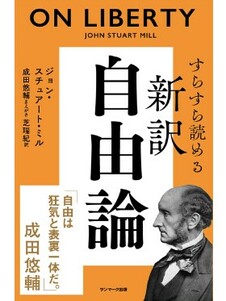「自由交易」の考え方
商売は社会的な行動である。なんらかの商品を売ろうとすれば、他者の利益、そして社会全体の利益に影響を与えることになる。
つまり、商売における行動は、原則的に社会が管理するものだと言える。そのため以前は、重要だと見なされるすべての商品について、政府が価格や製造法を定めるべきだと考えられていた。しかし、長きにわたる論争を経て、その風潮は変わった。
いまでは、生産者と売り手に完全な自由を与えてこそ、安価で質のいい商品が市場に出回ると認められている。唯一の条件は、買い手にも「買う場所を選ぶ自由」を与えることだ。この自由がなければ、売り手の暴走を防げないからだ。
以上は、いわゆる「自由交易」の考え方である。本書で扱ってきた「個人の自由」とは異なる根拠にもとづいているが、根拠がしっかりしている点は同じだ。
商売の制限と自由の対立
商売に制限を設けることも、商売のための生産に制限を設けることも、つまるところ「束縛」にほかならない。そしてあらゆる束縛は、束縛というだけで「悪」である。しかし、商売における制限は、社会が管理する行動だけを対象にするものだ。そうした制限を「間違い」だと言えるのは、求めた結果を出せなかった場合に限られる。
個人の自由の原理は、自由交易の考え方には含まれていない。そのため「自由交易の限界」についての問題ともほとんど関係がない。
たとえば、「粗悪品が詐欺まがいの方法で販売されるのを防ぐために、社会はどこまで人々を統制できるか」とか「危険な仕事に従事する労働者のために、衛生管理や安全管理をどこまで雇い主に強制できるか」といった問題に、本書で論じた原理がかかわってくることはめったにない。せいぜい、「人々を統制するか自由にさせるかのどちらかを選ぶとしたら、後者のほうが社会の利益になる」と言えるぐらいだ。とはいえ、先ほど挙げたような問題の場合、原則としてなんらかの統制が必要になることは確かだ。
一方で、商売への干渉にかかわる問題のなかには、自由の問題と重なるものもある。禁酒法の話もそれにあたるし、中国による阿片輸入の禁止や、毒物の販売に対する制限なども含まれる。いずれも「ある商品の入手を困難あるいは不可能にする」ことを目的にした干渉だ。こうした干渉に対しては、「生産者や売り手の自由への侵害」ではなく「買い手の自由への侵害」を根拠に反対することができる。