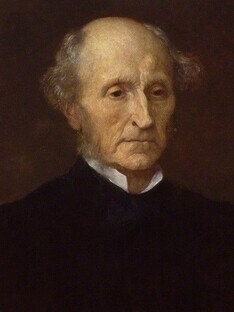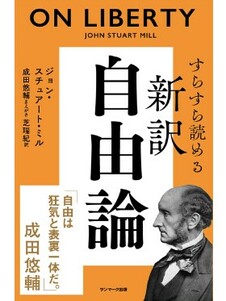犯罪や事故を防ぐ「自由の侵害」とは?
いま挙げた例のなかで、「毒物の販売」だけは別の問題につながってくる。「警察の機能」と呼ばれるものの限界はどこか、犯罪や事故を防ぐための「自由の侵害」はどこまで認められるのか、といった問題だ。
実際に発生した犯罪を摘発して罰を与えるだけでなく、犯罪を未然に防ぐことも政府の義務である。このことに異論がある人はいないだろう。だが、犯罪の予防においては、政府の権限が拡大解釈されやすい。犯罪を処罰するときに比べて、人々の自由が侵害される可能性がはるかに高いのだ。なぜなら、人々の「正当」な行動のなかに、「どのような犯罪にもつながらない」と言えるものはほとんどないからだ。
とはいえ、誰かが犯罪に手を染めようとしているのを目にしたなら、その人が犯行に及ぶまで待つ必要はない。警察はもちろん民間人でも、犯罪を防ぐためにその人の行動に干渉することが認められる。
もし毒物が、殺人以外に使い道がないものだとしたら、その生産と販売を禁止するのは100%正しいと言える。だが現実的には、合法的かつ有益な目的のために毒物が使われることもある。犯罪の防止のために毒物の販売を制限すれば、有益な行為までさまたげるかもしれないのだ。
繰り返すが、事故を防ぐことは政府の正当な義務のひとつだ。いまにも落ちかねない橋を渡ろうとしている人がいて、その人に警告する余裕がないときは、強引につかまえて引き戻してもいい。引き戻した人が警察官であれ一般市民であれ、その行為は「自由の侵害」にはあたらない。自由とはつまり、「望んだことをする自由」であり、橋を渡る人は「川に落ちる」ことを望んでいるわけではないからだ。
だが、その人が被害に遭うと確定したわけではなく、「被害に遭う可能性がある」だけだとしたらどうだろう? その場合、リスクを負うべきかどうかを決められるのは本人だけだ。その人がまだ子どもだとか、正常な判断ができない状態にあるとかいう場合を除いて、危険について警告する以上のことはしないほうがいい。
この考え方は、毒物の販売の問題にも適用できる。そうすることで、考えうる数々の規制のうち、どれが認められてどれが認められないかを判断できるようになる。
たとえば、「製品のラベルに危険性を明記する」ことを義務づけても自由の侵害にはならない。「買った商品が『有毒』だという事実を知りたくない」という買い手はまずいないからだ。しかし、「医師の証明書がなければ買えない」という規制ができたらどうだろう? 正当な使い道のために毒物を求める人からすると、余計な費用がかかううえ、購入事態をあきらめざるをえなくなる可能性もある。