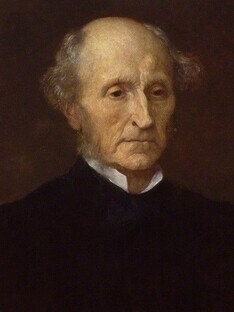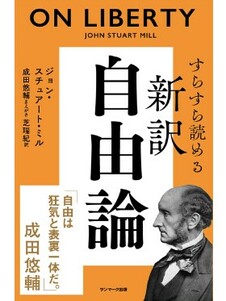「個人の自由」と「社会の規制」の境界線
非難されても仕方ないような行為でも、その影響が本人にしか及ばない場合、社会がそれを禁止したり罰したりするのは間違っている。
社会はあくまでも、個人の自由を尊重しなければならない。では、他人がそのような行為を勧めたり、誰かをそそのかしたりするのも、同じように「個人の自由」として尊重されるのだろうか? この問題はなかなかむずかしい。
他者に特定の行動をとるよう勧めるのは、個人的な行動とは言えない。「忠告」や「勧誘」は社会的な行動なので、他者に影響を与えるほかの行為と同様、社会によって規制されるべきだと思う人はおそらく多いだろう。
だが、その考えは間違っている。たしかに、他者になんらかの行動をうながすことは「個人の自由」ではカバーできないかもしれない。しかし、個人の自由の根拠になっている部分は、このような場合にも適用できるのだ。
“そそのかして”利益を得る場合は自由を適用できない
まず前提として、「本人にしか関係ないこと」を「本人がリスクを背負って」行うなら、なんの問題もない。ということは、どのような行動をとるべきかを誰かに相談するのも本人の自由でなければならない。意見を交換するのも、他者に助言するのもその人の自由ということだ。当然、「本人にしか影響しない行動」に限った話ではあるが。
話が複雑になるのは、助言を与える側が「他者をそそのかして利益を得ている」場合だ。つまり、社会や国において「悪」だと見なされる行為に人を巻きこみ、それによって金を稼いでいる人に対しては、自由の原理は適用できない。
そういうケースでは、また新しい要素が加わってくる。「公共の利益」と対立するものから利益を得て、公共の利益に対立することを生業とする人々の存在だ。そういう人たちに干渉することは、はたして正しいのだろうか?
売春や賭博をすべて取り締まる必要はないだろう。だが、売春の斡旋についてはどうか。賭博場を開くことは許されるのか。これは、「個人の自由」と「社会の管理」というふたつの原理のちょうど中間に位置する問題であり、どちらの原理を適用すべきかを判断するのは簡単ではない。どちらの側にも言い分があるからだ。