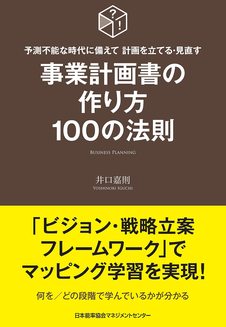「礼儀を重んじる」日本人の価値観
■価値観とは
価値観とは、人や組織が大切にしているものやことで、例えば、個人の場合ですと、物を大切に扱いなさいとか、弱い者いじめをしてはいけないとか、他人に迷惑を掛けないようにとか、みんなで仲良く等があります。
価値観は、人によって違う面もありますが、個人レベルの価値観、家族の価値観、コミュニティ・地域社会の価値観、会社・組織の価値観、国レベル・国民の価値観等それぞれのレベルによって価値観を共有する範囲、内容が異なります。
一般的には、個人レベルと会社・組織レベル、国民レベルの価値観がその差が一番大きく、違いが分かりやすいですね。
若い頃、結婚してみて食事や生活の価値観というか常識の違いに驚かされましたし、会社を変わって社風の違いに驚かされましたし、外国に行って、言語の違い以上に考え方や価値観・常識の違いに驚かされました。
このように、私たちは、基本自分を基準に判断しているので、考え方や価値観の違う人と生活したり、仕事をしたりすると、その違いに驚きますが、結局話し合いや相談を行って、折り合いを付けていくしかなくなります。
■日本人が大切にしている価値観
読者の皆さんにあえて日本人の価値観を説明するまでもないとは思いますが、客観的に捉えておくことも必要でしょうから、簡単にレビューしておきましょう。
一般に日本人の場合だと、礼儀を重んじます。相手に対して失礼なことをしてはいけないということで、これは非常に古くから維持されてきた価値観です。例えば、卑弥呼の時代に書かれた「魏志倭人伝」によると、倭(わ)国の人々(日本人)は、礼儀を重んじ、年長者を敬っていると書かれていて、2000年ほども前から日本人は礼儀を重んじていたことが分かります。
その礼儀の一つに、上下の関係を明らかにするということがあり、そのために敬語が使われます。ですから社会人になって敬語の使い方を間違えると、「あいつは礼儀を知らないやつだ」とか「敬語の使い方がなっていない」等と言われるのです。これらは、文化的な側面からの日本人の価値観といえます。
法律面で見ると、戦後の日本では、戦前の反省から、日本国憲法が新たに制定され、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が三大原則になりました。基本的人権の尊重は、平等権・自由権・社会権・参政権・請求権等からなりますが、例えば平等権でいうと「全ての国民は差別されずに平等である」という考え方を取っています。ですから性別や職業等で差別されてはいけないというのが、重要な価値観となっています。
国レベルでいうと、まず憲法が基本にあるのですが、企業でいうと、大切にしている価値観は、企業理念や経営理念に表現されているということになります。古い会社では、社是社訓などという言葉も使われているケースがあります。言葉は違いますが、指しているものは同じです。
例えば、パナソニックでは、創業者の松下幸之助が制定した「綱領」というものがあり、現在でもそれが受け継がれています。その綱領には、
「産業人たるの本分に徹し
社会生活の改善と向上を図り
世界文化の進展に寄与せんことを期す」
とあります。
少し古い表現ですので、現代風に解釈すると「ビジネスマンは本来行わなければならない仕事に集中し、世の中の人々の生活を改善、向上できるよう、また、世界の文化が発展していくことに貢献できるように心に誓います。」ということでしょうか。
他の企業でも、各社各様の企業理念があります。古い会社の場合、パナソニックのように創業者の言葉がそのまま引き継がれているようなケースもあります。有名な近江商人の「三方よし」(買い手よし、売り手よし、世間よし)というのは、江戸時代から続く近江商人の商売における基本的な価値観を表しているわけですね。
【Jグランドの人気WEBセミナー】
税理士登壇!不動産投資による相続税対策のポイントとは?
<フルローン可>「新築マンション」×「相続税圧縮」を徹底解説