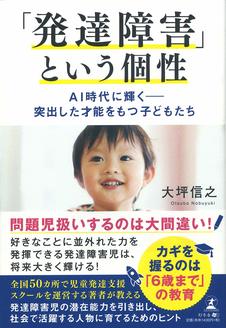なぜ、今「児童発達支援事業」が求められているのか…
>>>>>>>>記事を読む<<<<<<<<
子を叱ったら、ますます問題行動が増えてしまった…
発達障害による問題行動が起こったとき、それをやめさせようとして行きづまってしまうことがあります。言い聞かせたり、叱ったり、抑え込もうとしたり、やればやるほど問題行動が増えていくように感じることもありますね。
基本的な考え方は、「不適切な行動」の代わりとなる「適切な行動」の成功体験を重ね、スキルの獲得を目指していくことです。すぐにできることとして、視点を切り替え、パターンをくずすことを考えてみましょう。
発達障害の特性として、パターンにはまってしまうと、なかなかそこから抜け出せないという面があります。そのため、大人が意図的にパターンを変えてあげましょう。環境や大人の声かけを少し変えるだけでも、パターンをくずすことができます。そうすると、いつもと同じ行動をしなくなることもあるのです。
問題行動によって、一番困っているのは子ども自身かもしれません。大人がサポートできることとして、頭に置いておくべき考え方です。
「子どもの行動の変化を待つ」というのは、適切と思われる行動がなかなかとれず、子ども自身が葛藤しているときの対応です。「約束が果たせなかったらアレ(楽しみなこと)ができない」という対応は、罰の意味合いを持ってしまうので、こじれてしまった子どもの行動への対処としては適しません。しかし、ここで注意しなければならないのが、感覚刺激としての強化が含まれていないか、という点です。
たとえば、感情が高じた結果起こる、壁に頭を打つ(自傷)、人をたたく(他害)、あるいはものを投げるなどの行動のすべてに感覚刺激という側面があります。つまり、周りが反応しなくても、その行為自体に感覚的な快感が生じてしまい、繰り返すことにつながってしまうのです。
ですから、言葉で注意はせずに、すぐに制止して落ち着くのを待つ必要があります。行動には、それ自体が感覚を刺激する面が多くあることを知っておきましょう。
子どもとの「お約束」は慎重に行うべき理由
子どもが問題行動を起こすようになったとき、ついつい使ってしまいがちなのが、子どもと「お約束」をして行動を調整しようとすることです。
注目のセミナー情報
【資産運用】5月8日(水)開催
米国株式投資に新たな選択肢
知られざる有望企業の発掘機会が多数存在
「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力
【国内不動産】5月16日(木)開催
東京23区×新築×RC造のデザイナーズマンションで
〈5.5%超の利回り・1億円超の売却益〉を実現
物件開発のプロが伝授する「土地選び」の極意