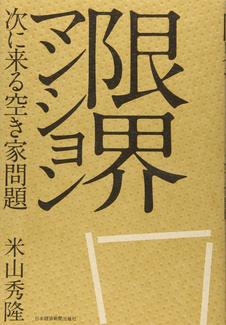高齢化、人口減少…昨今、マンションを取り囲む状況は極めて厳しいものになっています。大阪経済法科大学経済学部教授の米山秀隆氏の書籍『限界マンション 次に来る空き家問題』(日本経済新聞出版社)より一部を抜粋・編集し、マンションの建て替えの問題点を解説していきます。
【建て替え事例】マンション建て替えの現実
以下では、最近の事例で、建て替えに際し困難に直面しながら建て替えを行った2つのケースを簡単に紹介していこう。
■同潤会江戸川アパートメントのケース
第一のケースは、1934年に建築された「同潤会江戸川アパートメント」(新宿区、建て替え後の名称は「アトラス江戸川アパートメント」)の事例である。江戸川アパートメントは、同潤会アパートとしては最後に建築され、エレベーターやセントラルヒーティングも備え、竣工当時は東洋一のマンションといわれたほどであった。
近代的設備のほか、社交室や中庭、共同浴場、理髪室などが設置され、コミュニティ作りも重視された。
これ以前に建て替えられた同潤会アパートは、商業地域にあったことなどにより、第一種市街地再開発事業を活用することで、高い容積率を確保して建て替えを行い、区分所有者は等価交換で従来の面積以上を取得できた。
しかし、江戸川アパートメントは、住居系用途地域にあり容積を確保できないため(一部が既存不適格であった)、等価交換で取得できる面積(還元率)は50%程度に過ぎず、建て替えに際して住民の追加負担が生じざるを得ないケースであった。
つまりは、残り50%の分は自分で費用負担しなければ、同じ面積を確保できないということで、これまでのマンション建て替えでもっとも条件の厳しいケースであった。
江戸川アパートメントでは1960年代後半に建物の一部に傾きが生じたこともあり、1970年代初めから建て替えの検討が進められてきたが、なかなか具体化できなかった。1990年代には基本計画をまとめデベロッパーを選定しながらも、実現に至らなかった経線がある。
その後は自主再建を目指したが、全員合意を得られるメドも立たないまま、老朽化はますます進み、建て替えを急ぐ必要性が高まっていった。2000年以降は、再びデベロッパーの協力を仰ぐ方針に転換し、2001年にはデベロッパーを選定した。
その後、住民の意見を聴取して計画を作成し、2002年3月に、ようやく総会で建て替え決議を多数決で可決するに至った。
建て替え前の居住状況は、総戸数258戸のうち、区分所有者による居住、賃借人の居住、空き家・倉庫等がそれぞれ3分の1程度だった。区分所有者総数223名のうち、2002年3月の決議で賛成したのは192名であった(その後の話し合いにより賛成数はさらに増加)。
区分所有者の中には、高齢で建て替え費用を負担できないため、建て替え後に戻りたくても戻れない人もいたが、そうした人については、管理組合で管理する共用部分に住戸を設けて、低家賃で生涯住むことのできる仕組みを設けた(生涯借家制度)。
こうして、江戸川アパートメントは、築70年あまりでようやく建て替えられ、2005年に竣工した。建て替え後の総戸数240戸のうち、保留床として分譲されたのは106戸であった。
大阪経済法科大学経済学部教授
経歴
2020年9月~ 大阪経済法科大学経済学部教授
2020年8月~ 総務省統計局「2023年住宅・土地統計調査に関する研究会」メンバー
2019年10月~2020年8月 国立研究開発法人勤務
2019年4月~2019年9月 株式会社シンクダイン
2016年6月~2017年10月 総務省統計局「2018年住宅・土地統計調査に関する研究会」メンバー
2009年4月~2017年3月 高崎商科大学非常勤講師
2007年7月~2010年3月 慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所客員研究員
2004年2月~2019年9月 「ESPフォーキャスト調査」フォーキャスター
1996年4月~2019年3月 株式会社富士通総研
1989年4月~1996年4月 株式会社富士総合研究所
1989年3月 筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了(経済学修士)
1986年3月 筑波大学第三学群社会工学類卒業
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「マンション限界時代」スラム化していくマンションたち