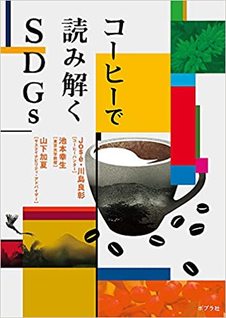一時的な成功物語がもたらした苦しみ
1994年と1997年のコーヒー価格高騰の恩恵を受けたのがベトナムでした。1986年に「ドイモイ(刷新)」と呼ばれる自由化政策を採用して市場経済の導入に舵を切ったベトナムは、米やコショウ、そしてコーヒーの生産量を飛躍的に増やすことに成功しました。

そんなベトナムの追い風になったのは、世界のコーヒー供給量を調整してきた国際コーヒー協定が1989年に崩壊したことです。これによって各国の輸出量の上限が事実上撤廃されたため、大量に生産して大量に輸出することが可能になったのです。
ブラジルで生産されるコーヒーはその7割が「アラビカ種」ですが、ベトナムの主要なコーヒーの産地である中部高原は標高600メートル程度と低いため、生産されるのはそのほとんどが低地でも栽培可能な「ロブスタ種」です。ロブスタ種は、風味の面ではアラビカ種に劣るものの、病気に強く、栽培に手間がかからないため、アラビカ種より生産コストをずっと安価に抑えることができるという強みがあります。
しかも、勤勉で研究熱心なベトナム人の国民性によって、1ヘクタール当たり2~3トンにものぼる高い生産性を実現させたため、高いコストパフォーマンスを実現しました。
単純な比較はできないものの、他の国々では1ヘクタール当たり1トンというのが平均的な値であることを考えれば、これは脅威的な数字だと言えるでしょう。古くからコーヒーの栽培を続けてきたラムドン省のある村は、1994年と1997年のコーヒー価格の高騰の恩恵を存分に受け、「コーヒー長者村」と呼ばれるまでになりました。
大金を手にした人々は家を建て替え、村の学校も立派なものに建て替えられました。中には「コーヒー御殿」と呼ばれるほどの立派な家を建てた人もいたと言います。このような成功を収めた「コーヒー村」が、中部高原にはたくさん生まれていたのです。
「コーヒー村」での成功物語はベトナム全土に知れ渡り、同じように成功を夢見る人たちが次々と中部高原にやってきては、コーヒー樹を植え始めました。最初は単身でやってきて、収入が増えたのちに家族を呼び寄せた人も多かったそうです。
人口密度が高く、1人当たりの農地面積がとても狭いベトナム北部の紅河デルタ地方の人から見れば、広大な中部高原は、まさにフロンティアだったのです。新たにコーヒー農園を始めようとすれば、当然資金が必要です。家を売り払ったり、借金をした人もいたでしょう。それも軌道に乗るまでの辛抱だと、きっと多くの人は楽観的に考えていたに違いありません。