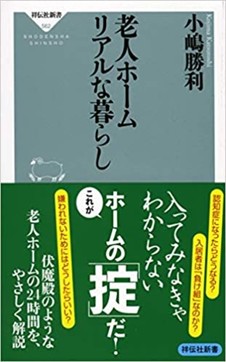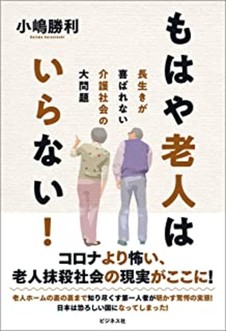介護職員にまともな職員は本当にいないのか?
前回まで、介護職員には期待をするなとか、介護職員にはまともなコミュニケーション能力がないとか、言いたいことを言ってきましたが、はたしてまともな介護職員など世の中には存在しないのでしょうか?
当たり前の話ですが、心ある介護職員は存在しています。私も、何人もの頭が下がる介護職員を見てきました。しかし、心ある介護職員は、今や絶滅危惧種になっているように思えてなりません。その理由をこれから説明していきます。

老人ホームの多くは民間の営利団体が経営しています。何を今さらという読者の方も多いでしょうが、この部分がとても重要な部分になります。当然、営利企業が運営しているので、経営にとって最優先される事項は収益になります。これもまた当然の話ですが、収益が悪ければ銀行からも相手にされず、老人ホームは潰れてしまいます。
しかし、現場で働いている介護職員の多くには、この収益構造が見えません。長く空室が続いているような老人ホームであれば、介護職員であっても、うちのホームは大丈夫なのだろうか?と思うでしょうが、現実はそう簡単な話ではありません。したがって、自社がどの程度の収益状態なのかはわからないまま仕事をしているということになります。
目の前の入居者が具体的に困っているのなら助けてあげたい。これは多くの介護職員の欲求ですが、現実には助けてあげることができず、多くの場合、我慢してもらうことのほうが多いと思います。
理由は簡単です。職員の配置が少なく、そこまで手が回らないからです。勘違いをしないでください。介護職員の配置が少ないというのは、人手不足で少ないのではなく、運営コストの中で一番ボリュームが大きい職員を多く配置していると収益が悪化してしまうからなのです。つまり、経営を考えた場合、職員コストは必要最低限に抑える必要があるということであり、ここのコスト管理が甘くなると赤字体質になってしまいます。