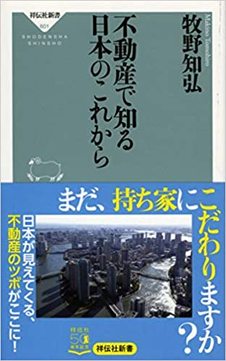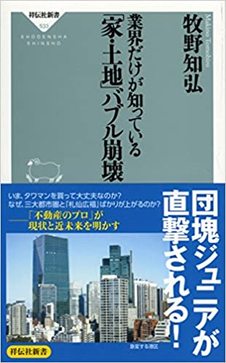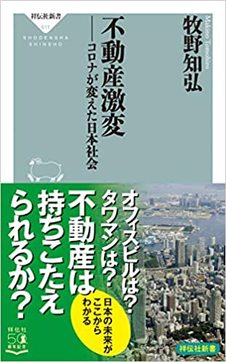市民権を得た「ネットスーパー」はどこまで伸びるか
商業施設の多くが業態転換する
ポスト・コロナ時代の商業施設はどうでしょうか。コロナ禍において大いに威力を発揮したのがEC(電子商取引)でした。ECの世界では人と人とが直接触れあうことなく、買い物をすませることができるため、感染症の恐怖に怯える世の中では高い評価を得ることができました。
商業施設の歴史を振り返ってみると、商取引は物々交換から始まり、貨幣ができると貨幣を通した取引が活発になります。それが街の形成を育み、取引の効率化を求めて多くの商店が同じ場所に軒を連ねるようになります。

日本国内にも多くの商店街がありますが、商店街には個人商店が立ち並び、お客さんは商店街に来れば一日のほぼすべての用件をすますことができるようになりました。やがて、ワンストップで日常のすべての買い物をすますことができるスーパーマーケットが登場し、個人商店を駆逐していきます。
スーパーは商店街のそれぞれの商店が売っていた品物、とりわけ食料品を中心に、そのすべてをスーパーという「棚」に陳列してしまいました。スーパーは食料品のプラットフォームをリアルな空間で実現した売り方であったと言えます。
これを物流の力を借り、より大きなプラットフォームをこしらえて参入したのが、EC取引でした。アマゾンは、当初は書籍から取り扱い始めたと言われています。書籍は、食料品のように腐ったりしないので扱いが容易でした。取扱商品はやがて文房具や家具家電品にも及び、およそ生活に必要なほとんどすべてのものがプラットフォームに乗っかる形で誰でもがサイトにアクセスすることで商品を購入することができるようになりました。
ただ、食料品については、品質保持の問題、配送料の問題などから、スーパーには太刀打ちすることが難しい領域でした。ところが今回のコロナ禍で人々は、飲食店からはデリバリーサービスで食事をオーダーするようになりました。そしてネットスーパーを駆使して、食料品も取り寄せるようになりました。そして、いちいち「密」であるスーパーに赴かずとも注文した食材が配送されるネットスーパーが品質も悪くなく、しかも便利であることに気づいたのです。自分の目で見て確かめないと、食料品の品質は見抜けないと思ってきた「常識」が覆されたのです。
人々の働き方が変わり、在宅勤務をする人が増えてくれば、ネットスーパーはかなりのポジションをつかむようになると思われます。通勤に使っていた時間の無駄に気づいた人たちが、日常の食料品を買うためだけにスーパーに行く時間も「無駄」とか「もったいない」と感じるようになると、おそらくこの領域のビジネスはますます拡大していくことでしょう。