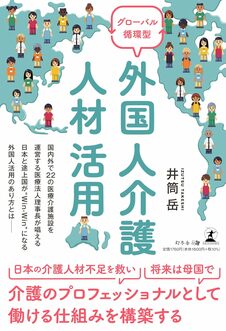外国人介護人材が人材不足の解決の糸口となる
介護人材の不足が深刻になるなか、その有力な打開策の一つが外国人介護人材の活用です。日本国内で人材が確保できないのであれば、海外から新たに人を呼び込もうというわけです。
近年、日本では女性の社会進出や定年退職後の再雇用が進み、労働人口自体は増加してきました。ただ、労働人口自体は増えているものの、15~64歳の生産年齢人口はピークであった1995年から減少の一途をたどっています。
特に若い世代の減少が進んでおり、新成人の数の推移を見てみると、2024年の新成人は106万人で総人口に占める割合は0.86%にまで落ち込んでいます。前年と比べても6万人減少しており、人数も割合も過去最低を更新しました。
若者を採用して育てていきたいと考えても、そもそも若い世代の人口自体が少ないなかでは難しいという状況にあります。この傾向は少子化のために今後ますます進むことが予想されます。
そこで、日本政府は外国人介護人材の活用を推し進めようと、介護に関する在留資格を増やしてきました。
在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在し、活動できる範囲を示したものです。そのため、合法的に日本に滞在しているすべての外国人はなんらかの在留資格を取得していることになります。在留資格には、就労が認められるものもあれば認められないものもありますし、就労の可否は活動内容によるものもあります。
また、永住者や日本人の配偶者などの身分・地位に基づくものもあります。それらのなかで、介護人材に関するものは「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動(EPA)」です。
在留資格は、一度取得すればよいというわけではありません。活動内容や身分が変わることがあれば、それに応じて在留資格を変更する必要が生じます。
例えば、日本の学校に入学した一般的な外国人学生の場合で考えてみると、学生として学校に通っている時点の在留資格は「留学」です。
しかし、卒業して就労するようになったら「技能」に切り替えなければなりません。在留資格ごとに、従事できる業務内容が決まっているため、仕事の内容が多岐にわたるのであれば、それに合わせて在留資格を取得することになります。
その後、もし経営者になることがあれば、「経営・管理」への切り替えが必要になりますし、日本への永住を決意したときに一定の要件を満たしているようなら「永住者」を取得することもできます。
介護の場合は特定活動のEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者として来日した人が、介護福祉士の国家試験に合格して在留資格「介護」に切り替えて就労したり、技能実習で来日した人が実習期間終了後に特定技能に移行したりといったケースがあります。