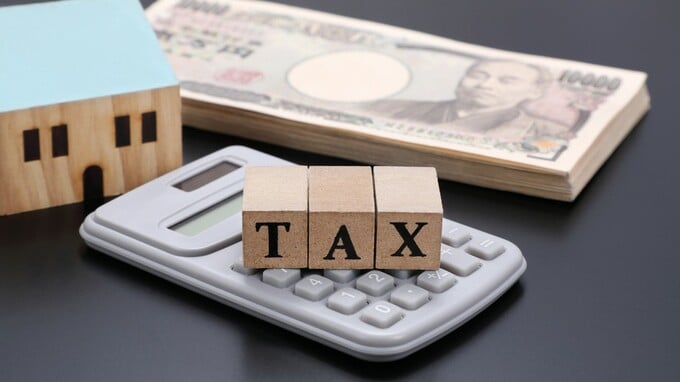「相続時精算課税制度」の基本
相続時精算課税制度は贈与税がかからない特例の中でも利用する人が多い有名な特例です。相続時精算課税制度の基礎知識を確認していきます。
祖父母や父母からの生前贈与に適用できる
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫)へ贈与をする場合に、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度のことです。また2,500万円を超える金額を贈与した場合でも、2,500万円を超えた分に対して一律20%の贈与税ですみます。
しかしながら、「相続時精算課税」という名称のとおり、贈与者が死亡して相続が発生した場合には本制度を利用して贈与した金額を故人の相続財産に加算して相続税を計算します。したがって、原則として相続税の節税対策にはなりません。
ただし2,500万円を超える部分について支払った贈与税は将来の相続税から控除することができます。相続財産の前渡しとイメージすると分かりやすいと思います。
また一括で2,500万円を贈与しなければならないわけではなく、生涯にわたり2,500万円の贈与税の特別控除額を使うことができます。特例を利用したケースの時系列を具体例でみてみましょう。
具体例:父63歳から子25歳へ相続時精算課税制度を利用した贈与を実施
●初年度:1,200万円を贈与
●3年後:500万円を贈与
●10年後:1,000万円を贈与
→贈与累計が2,700万円となり2,500万円を超えた分の200万円×20%=40万円の贈与税が発生
●15年後:父死亡
→父の相続財産に過去に相続時精算課税制度を利用して贈与した累計2,700万円を合算し、既に支払っていた贈与税40万円を相続税から控除する
このように相続時精算課税制度を適用すると生涯にわたり2,500万円までの贈与は無税となりますが、最終的には相続税で生前贈与財産が加算されることになります。まさに特例の名称通り、生前の贈与分を全て相続時に精算するということです。
【令和6年から】基礎控除110万円も使える
令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除額が適用できます。この基礎控除額は2,500万円の特別控除額とは別のものとして扱われ、基礎控除を行った部分は、贈与者が死亡して相続が発生した場合に故人の相続財産に加算しません。改正後の税額計算について、先ほどの具体例をもとに解説します。
具体例:【令和6年以降】父63歳から子25歳へ相続時精算課税制度を利用した贈与を実施
●初年度:1,200万円を贈与 →基礎控除後の1,090万円が特別控除の対象
●3年後:500万円を贈与 →基礎控除後の390万円が特別控除の対象
●10年後:1,000万円を贈与 →基礎控除後の890万円が特別控除の対象
贈与累計は2,700万円であるが、特別控除の対象は2,370万円となり2,500万円を超えない。したがって贈与税は発生しない。
●15年後:父死亡
→父の相続財産に過去に相続時精算課税制度を利用して贈与した累計2,370万円(基礎控除後)を合算する。既に支払っていた贈与税はないので、相続税からは控除しない