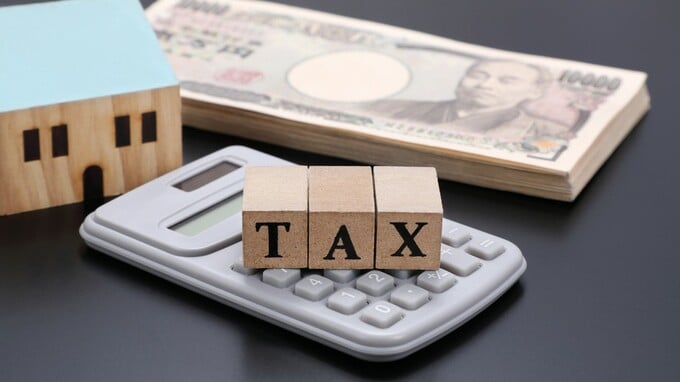「相続財産が1億円以下」の人は相続時精算課税制度の利用も
相続時精算課税制度のデメリットは、生前贈与した財産が相続の際に相続税の対象になることです。また、この制度を利用すると後の相続の際に贈与した額が相続財産に加算されることになり、不足する相続税を支払わなければなりません。
しかし、たとえば子供や孫が家を買うなど大きい金額が必要な時には年間110万円の贈与では十分に援助してあげることができません。長期間かけて毎年110万円の贈与を行う計画だったとしてもそれを毎年計画的に継続して行うのはなかなか難しい面もあります。
相続税がかかるとはいえ、相続時精算課税でまとまったお金を贈与税がかからず贈与することができるのは魅力的と言えます。下記の図をご覧ください。相続財産が1億円以下の場合には相続税の負担はそこまで大きくはありません。
贈与する側、贈与を受ける側で考えが異なるとは思いますが、家を買おうとした時に後々相続税を負担してもいいから2,500万円の贈与を受けたいと考える方もいるかと思います。その場合は相続時精算課税制度を利用するとよいでしょう。逆に相続財産が2億円、3億円となる場合には相続税の負担も大きくなるため相続時精算課税制度の利用は慎重に考える必要があります。
「税務署への申告方法」と「必要書類」で知っておくべきこと
この章では具体的に税務署へ相続時精算課税制度を適用して申告を行う際の、申告書の書き方や必要書類をご紹介します。
相続時精算課税制度適用申告書の記載例
相続時精算課税制度を適用する場合には、以下の書類を作成する必要があります。これら書類の作成は税理士に依頼した方が確実ですが、書き方はそれほど難しくないため自分で作成することもできます。
■贈与税の申告書
これまで述べてきた通り、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。しかし、贈与税がかからない場合であっても贈与税の申告書を作成する必要があります。①いつ、②誰から、③どんな種類の財産を、④いくらもらったか、という内容を記載する書類となります(令和6年以降は、年間の贈与額が基礎控除額110万円以下であれば申告書の提出は不要です)。
■相続時精算課税選択届出書
財産をもらった(贈与を受けた)方が、今年以降、今回財産の贈与を受けた方からもらう財産についてはすべて相続時精算課税制度を適用するということを宣言する書類となります。この制度を一旦適用すると、適用を取り下げることができないため、確認を取るための意味合いが強い書類です。
申告時に必要な添付書類
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。この際に、次の書類を添付することとされています。
<相続時精算課税制度の申告時必要書類>
次の情報が分かる受贈者(贈与を受けた人)や贈与者の戸籍謄本又は戸籍抄本
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
令和元年分の申告までは、受贈者、贈与者の住所等を証明する書類として戸籍の附票や住民票を提出する必要がありましたが、令和2年分以降は不要となりました。
2年(回)目以降の申告では添付書類は必要ない
相続時精算課税制度を使って行う贈与は、年を跨ぎ複数回行うことができます。回数や一回あたりの金額に制限等はなく、特別控除額2,500万円という上限が決められているだけです。たとえば、1年目に1,000万円、2年目に500万円、4年目に1,000万円というような贈与の仕方も可能です。そこで、1年目の贈与税申告の際にすべての添付資料を提出した場合においては、2年目、4年目に関する贈与では、重複する書類については添付が不要となります。贈与税の申告書のみ、内容が異なりますので毎年記載し提出する必要があります。それ以外の、相続時精算課税選択届出書、戸籍謄本については再度提出する必要はありません。
なお、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除額があるため、年間の贈与額が110万円以下の場合は申告不要となります。
必要書類の入手方法
各必要書類の具体的な入手方法をご紹介したいと思います。基本的には、税務署と役場に行けばすべての資料を揃えることができます。
(1)「贈与税申告書」「相続時精算課税選択届出書」の入手方法
これらの書類は、税務署に用紙が備え付けられています。また国税庁のホームページより様式をダウンロードして使用することも可能です。国税庁のホームページ「贈与税(贈与税の申告書作成コーナー)」から「様式一覧」に進んで頂き、「申告書第1表」と「第2表」、「相続時精算課税選択届出書」というPDFをダウンロードしましょう。
(2)「戸籍謄本(抄本)」の入手方法
戸籍謄本(もしくは抄本)については、本籍地のある市区町村役場の戸籍係で取得する必要があります。なお、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まり、近くの市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになっています。
難しいと感じた場合には申告や資料収集の税理士への依頼を検討
相続時精算課税制度を使った贈与税申告に関わる書類作成・取得等の一連の作業は、ご自身で行うことも十分に可能です。実際にご自身で行われている方が大半であるというのが実情です。ただ、それはあくまで現預金を贈与する場合に限ります。簡単に言うと、たとえば1,000万円を贈与した場合には、「父から1,000万円をもらいました」と書類に記載し、戸籍謄本等の添付書類を集めて税務署に提出するだけの手続きだからです。
気を付けなければいけないのは、土地を相続時精算課税制度で贈与する場合です。その場合、土地を金銭的価値に見積もる(評価する)必要があります。土地の相続税評価については税理士でさえ難しいとされていますので、一般の方が正確に評価を行うのはとても難しいと言えます。この土地の評価を誤ると後々、税務署の指摘を受け余分な税金を支払わなければならない事態も生じかねません。
もしご不安があれば、税理士にすべてお任せしてしまうというのも一つの手です。税理士に依頼すれば、申告書類の作成はもちろん、戸籍謄本等の役所で取得する書類も職権で取得してもらうことができご自身で役所に赴く必要がありません。税理士によって報酬は異なりますが、戸籍関係の書類の取得代行から申告書の作成まですべて依頼する場合、費用は10万円程度になります。
土地の評価に誤りがあったり、書類の記載不備、添付資料の不備があったりすれば、本来かからないはずの多額の税金がかかってくる可能性もあります。手間の観点だけではなく安心を得るという観点でも、税理士に手続きを依頼するメリットは十分にあると言えます。