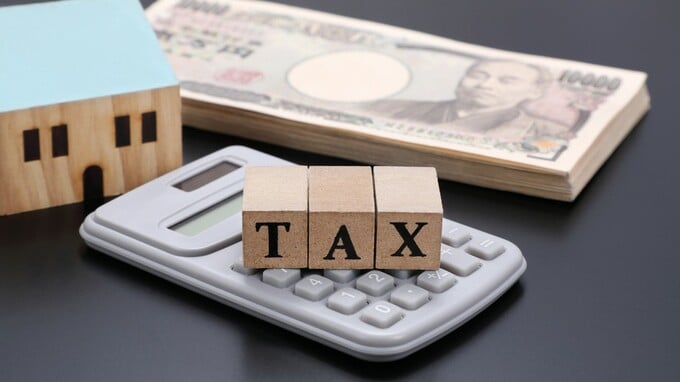「特例を利用するのに適した」具体的なケース
ここまで相続時精算課税制度の基礎知識やメリット・デメリットを解説してきましたが、では一体どんな方なら特例を適用することでメリットが受けられるのでしょう? ここでは実際に特例を利用するのに適した具体的なケースを紹介します。相続時精算課税制度はメリットとデメリットの両方がある制度ですので下記にあてはまるような方は利用を検討してみるとよいでしょう。
(1)相続税がかからない人
相続時精算課税制度を利用すると、贈与した財産が相続発生時に相続財産に加算されて相続税が計算されてしまいます。しかし、そもそも相続税がかからない(財産が3,000万円+法定相続人の人数×600万円以内)人は加算されても相続税は発生しません。
たとえば相続税がかからない3,000万円程度の財産をお持ちのAさんが、子供がマイホームを購入する際住宅ローンの頭金500万円を援助するとしましょう。500万円をそのまま贈与してしまうと贈与税が50万円ほどかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までは無税で贈与でき、贈与税の負担がありません。
またAさんは将来相続税がかかるほどの財産を持っていないため、相続時に500万円が加算されても相続税に影響はありません。こういった方にとっては一時的に多額の財産を贈与税の負担なしに贈与できるため、この特例を利用することでメリットがあります。
(2)収益不動産を保有している人
相続時精算課税制度を使って収益不動産を贈与して、賃料収入の蓄積を防ぐことで相続税の節税対策をとる方法です。収益不動産を所有しておりこれ以上相続税の対象となる財産を増やしたくない人に適しています。具体例を紹介します。
【具体例】
・父Aさん(60歳)、子Bさん(30歳)
・父Aさんは資産家で複数の賃貸マンションを経営
・このままだと賃料収入が父Aさんに蓄積され将来の相続税対象となってしまう
⇒そこで相続時精算課税制度を利用して父Aさんの賃貸マンションの建物(2,500万円)を子Bに贈与
【対策による効果】
賃料収入は建物の所有者に帰属するため、建物が子Bさん名義に変わったことで子Bさんの財産として蓄積され、父Aさんの相続財産の増加を防ぐことができました。このように資産家の方でこれ以上の財産の増加を防ぎたい場合は、相続時精算課税制度を利用して収入がある不動産を贈与することで相続税を節税することができます。
(3)子や孫への事業承継を考えている中小企業オーナー
中小企業オーナーが保有する自社株式は会社の業績があがれば相続税評価額も高くなります。そこで今後の成長が見込まれるような場合には、相続時精算課税制度を利用して後継者候補の子に自社株式を贈与することが多くあります。
たとえば現状の自社株式の価値が5,000万円で今後の急成長が見込まれる場合、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うと、
の贈与税を税務署に支払うことになります。その後、会社が成長し相続発生時点で自社株式の相続税評価額が2億円になっていた場合、贈与を行わず相続した場合は2億円が相続税の課税対象となります。しかし、相続時精算課税制度を利用していた場合は相続税の対象となる価額は贈与当時の5,000万円ですので、株価上昇分の1億5,000万円は相続税の対象とはならないのです。
このように中小企業オーナーが今後の自社株式の成長を見越して後継者へ早めに株式を贈与する際に大きな効果を発揮するのです。さらに、事業承継税制と併用すれば、自社株式の贈与に対する贈与税の納税が一定の要件のもと猶予されます。