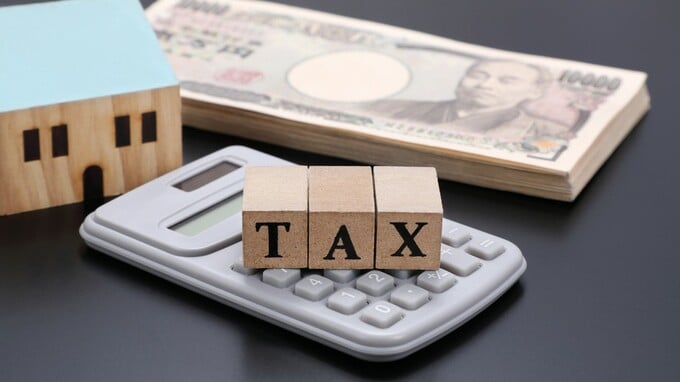併せて押さえておきたい住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
マイホームの購入を考えている子や孫がいる場合には相続時精算課税制度と併せて押さえておきたい特例の中に、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例というものがあります。令和8年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫)が住宅を購入するための資金やリフォームの資金を受け取った場合に、一定額まで贈与税が非課税になるという特例です。
贈与税が非課税になる限度額は、下記のとおりです(令和4年1月1日以後の贈与の場合)。
省エネ等住宅 1,000万円
それ以外の住宅 500万円
相続時精算課税制度と比較して大きな2つのメリットは、「相続時に持ち戻し加算しなくてもよい」「暦年贈与は引き続き利用できる」という点にあります。非課税限度額は購入する住宅の種類や年度によって異なり、最大でも1,000万円までと相続時精算課税制度よりは金額が大きくありませんが、マイホーム購入時や大規模リフォーム時には利用を検討するとよいでしょう。
また相続時精算課税制度と併用することもできるため、マイホーム購入やリフォームへの資金使途であれば、まずこの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を適用し、さらに上乗せで相続時精算課税制度を適用するかを検討するとよいでしょう。令和8年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を行う場合は、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を適用できます。