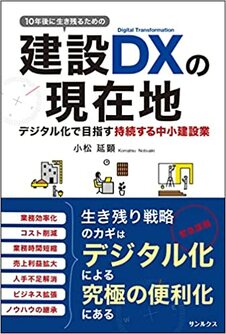デジタル化で「受注率」だけでなく「規模」も拡大
デジタル化によってもたらされる恩恵を、実際の例に沿って紹介していきましょう。
舞台となったのは、社員3名程度の空調設備工事のA社です。空調設備工事といってもメイン顧客は一般家庭などエンドユーザーではありません。ビル管理会社や、ビルや住宅の設計建築を受託する元請の工務店や建築会社です。A社は、これらの企業の下請けとして、業務を受注してきていました。
A社の業務は、まず元請からのご相談後の現地調査から始まります。新築の場合はゼロからの打ち合わせになりますが、既存の建築物でエアコンを入れ替える場合であれば、現在使っている型番、台数、設置場所を調査し、新規でどう入れ替えを行うかの提案をしていくことになります。調査の記録は、主にペーパー上で記入していました。調査現場で記入された記録用紙をもとに、社に戻ってから既存の型と同等以上の適切な商品を選定し、作成した見積書を元請に提案します。
そして、それをもとに、元請はA社への発注を正式に行うかどうかを判断していくことになります。今回の例は空調設備工事会社ですが、建築業界全般で下請けの企業の動き方としては大きくは変わらないのではないでしょうか。
結論からいうと、このA社、デジタル化を促進することによって、この後の受注率が大幅にアップすることになります。それにともない、従業員数も10倍以上の40名規模にまで成長しています。
いったい、デジタル化がA社にどのような変化をもたらしたのでしょうか? 視点を変えて、元請目線で考えてみましょう。
元請からすると、お付き合いのある空調設備工事業者は当然このA社だけではありません。ほかにも数社、A社にとっては競合となる企業とコンスタントに付き合っているのは当然のことです。
案件や時期によってケースバイケースで業者を使い分け、時には相見積をとって、自社にとってより有益な条件下になるように考えてもいくでしょう。相見積を出す際は、各社から届いた見積内容や、対応方法などを吟味し、総合的に判断して最終的な発注先を決めていくはずです。
ここで、デジタル化したA社に最初の恩恵が出てきます。ペーパー記入の場合は、現場で記録したペーパーを一度自社に持ち帰る必要があります。なぜならば、現場での記入はあくまでメモであり、自社に戻らないと正確な見積を出す作業ができないからです。
例えばお昼ごろに現地調査に行くとしましょう。調査が終わって社に戻ると、その日の業務時間はほとんど残されていません。見積を作るための商品の選定や、見積作成そのものは、どう急いでも翌日、もしくは翌々日になってきます。場合によってはもっとかかるかもしれません。