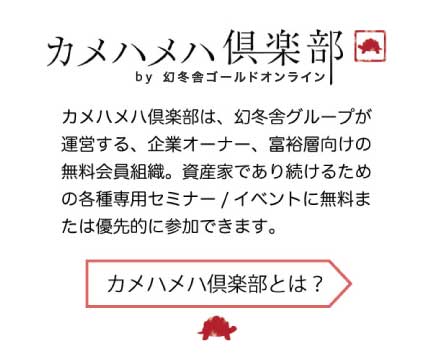禁止事項を定めるべき理由
利用規約には、提供するサービスの態様に応じて、ユーザーに禁止すべき事項を明確に定めておくべきでしょう。
なぜなら、禁止事項が定められていなければ、サービス提供者である事業者が行ってほしくない行動をユーザーが取ったとしても、退会や投稿削除などの措置をとることが難しくなるためです。
ユーザーの行為がいくらサービス提供者である事業者が望まない行為であったとしても、規約などの根拠なく強制退会などの措置を取ってしまえば、ユーザー側から損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、禁止事項を定めないことで、ウェブサイトが荒れてしまう可能性もあります。
たとえば、異性との出会いを目的とするウェブサービスではないにもかかわらず、ユーザーが異性との出会いを求めるような投稿を繰り返した場合には、他のユーザーの健全な利用が妨げられてしまうでしょう。
そのような場合であっても、利用規約にこのような投稿が禁止事項であると定めていなければ、対処が困難となってしまいます。
違反者への制裁時に注意すること
ユーザーが利用規約違反をした際、制裁措置を取る場合には、次の点に注意しましょう。
ユーザーの損害賠償額を一方的に規定した条項は無効
先ほども解説したように、いくら利用規約に損害賠償予定額を定めたところで、その額が実際に事業者に生じた損害を超える場合には、その額をユーザーへ請求することはできません。
仮に損害賠償予定額を根拠に実際の損害より多額となる損害賠償を請求したとしても、相手方から反論される可能性が高いほか、場合によってはSNSで炎上してしまったり、他のユーザーが離反してしまったりするリスクがあるでしょう。
そのため、利用規約に定めた損害賠償の予定額を根拠に制裁を課そうとする際には、あらかじめ弁護士へ相談することをおすすめします。
消費者の利益を一方的に害する条項は無効
利用規約は自由に定めることができるわけではなく、先ほど解説をしたように消費者契約法や民法の制約を受け、相手方の利益を一方的に害する不当条項は無効となります。
仮に制裁の根拠となる条項が不当条項に該当していれば、制裁しようとしたユーザー側から制裁自体が無効であると主張されたり、損害賠償請求をされたりしてしまうリスクがあります。
そのため、ユーザーへ制裁措置を課そうとする際には、あらためて利用規約を見直し、根拠となる条項が消費者契約法などの不当条項に該当しないか確認する必要があるでしょう。
そもそも利用規約に同意を得ていたか
いくら事業者が利用規約を定めていても、利用規約を契約内容とすることに対するユーザーの同意が得られていないと判断されれば、その利用規約に沿って制裁を課すことはできません。
利用規約が契約内容とされるためには、冒頭で解説したように、申し込みに際してユーザーの同意が要件となるためです。
たとえば、単にウェブサイト上に利用規約を設置してユーザーがいつでも見られる状態になっていたというのみでは、利用規約への同意を得ているとはされない可能性があります。
利用規約違反をしたユーザーに制裁を課そうとする際には、その利用規約を契約内容とすることに同意を得られていたかどうか、あらためてウェブサイトの設計を確認しておくべきでしょう。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資