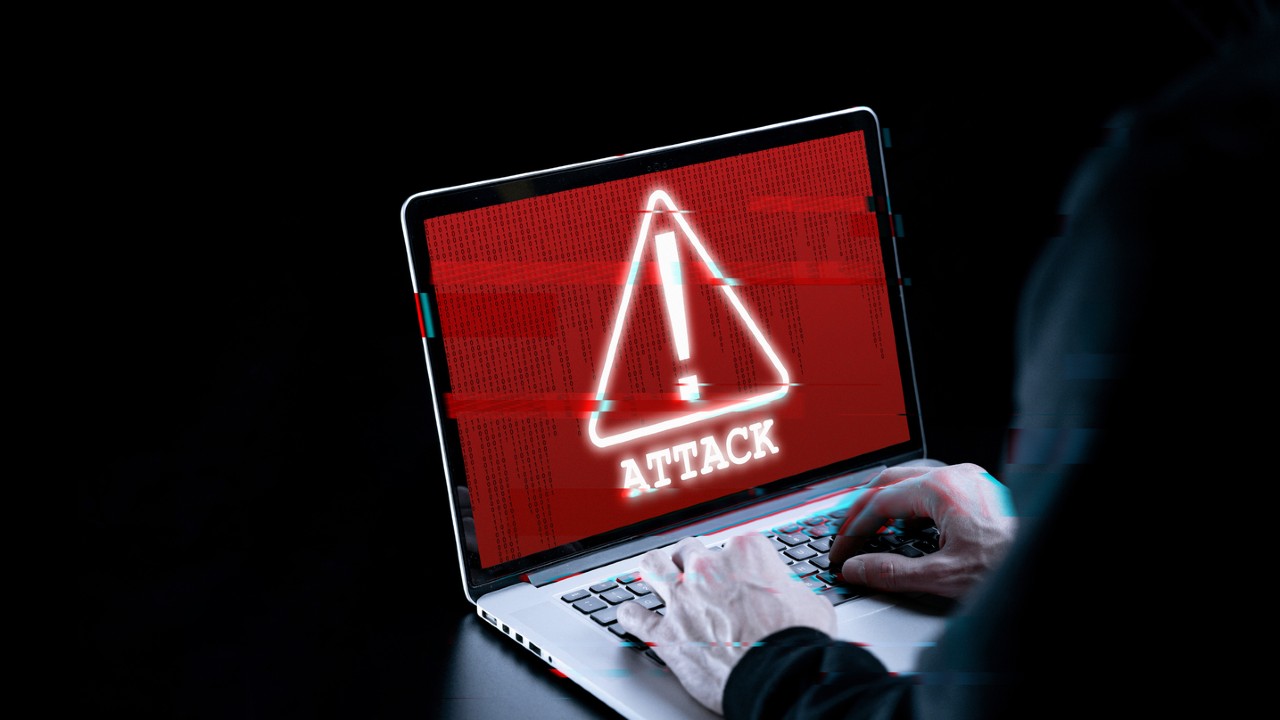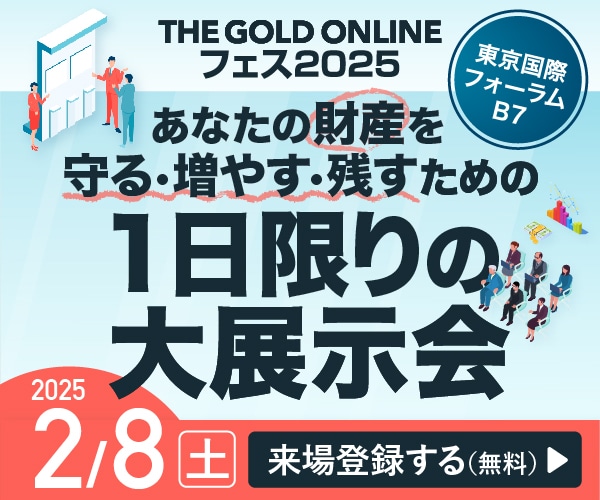違反者にはどんな制裁ができる?
利用規約違反者への制裁としては、どのようなものが挙げられるでしょうか? 主な制裁は、次の2パターンです。
強制退会など
最も一般的な制裁措置は、強制退会やアカウント停止です。ウェブ上で不特定多数に提供されているサービスの場合、利用規約違反者に対して、アカウントの一時停止や、強制退会措置を取るとしているケースが多いでしょう。
なお、ユーザーが課金をする可能性があるウェブサービスの場合には、強制退会に伴って課金額の返還に応じるかどうかについても定めておいたほうがよいでしょう。
また、月額の利用料などが発生するサービスの場合には、強制退会による利用料の返還の有無についても規定しておくと安心です。
ただし、仮に課金額を一切返還しない旨を定めた場合であっても、違反の態様や返還しない課金額などによっては、不当条項として無効となるおそれがあります。
損害賠償請求
利用規約違反により、事業者に損害が発生した場合には、違反ユーザーに対して損害賠償請求をすることが可能です。請求できる金額は、実際に事業者に生じた損害となります。
なお、利用規約中に、たとえば「本規約に違反した場合には、金10万円を請求する」などと損害賠償額の予定を定めているケースも散見されますが、これは消費者契約法により制約が加えられる可能性が高いため注意が必要です。
消費者契約法によれば、このような損害賠償額の予定は、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効となります。
この条項は、解釈の余地がかなり広く、裁判例も様々なものがあり、また、裁判になった場合の主張・立証もかなり大変ですので、一概にいくらくらいということを明示することがかなり困難であるというのが現状です。
不当条項規制の重要性
利用規約を作成する場合には、不当条項規制に注意しなければなりません。なぜなら、いくら利用規約に定めていても、利用規約の条項が不当規約に該当すると判断されてしまえば、その条項は無効とされてしまうためです。
また、不当条項である利用規約に沿って制裁を課した場合には、むしろ事業者側が相手方から訴えられてしまう可能性があるでしょう。不当条項に関する規制は、消費者契約法と民法にそれぞれ定められています。
消費者契約法による利用規約の規制
消費者契約法によれば、民法等の法律の規程が適用される場合と比較して、消費者の利益を一方的に害する次のものが、不当条項に該当します。
・消費者の義務を加重する条項
これらに該当する条項は、いくら利用規約で定めても無効となります。
定型約款による利用規約の規制
民法の規定によれば、定型取引の態様および実情並びに取引上の社会通念に照らして、相手方の利益を一方的に害する次のものが、不当条項となり得ます。
・相手方の義務を加重する条項
これらに該当する条項は、いくら利用規約で定めてユーザーの同意を取ったところで、合意をしなかったものとみなされます。つまり、これらの条項は無効であるということです。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!