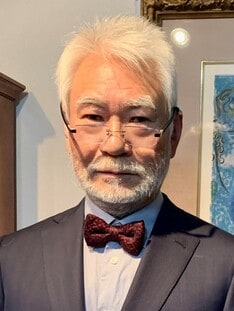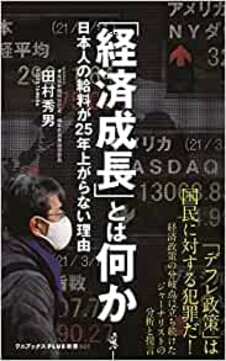バブルだと判定できる基準はないという結論
■バブルとは?
バブルは金融市場あるいは不動産市場に関する金融現象です。前者の典型的な例は株式です。株価がどんどん上がる。それでバブルかというと、さしたる定義や計算方式はないのです。ただ後講釈で、やっぱりこんなに利益が下がっていたのに株価が上がったのはおかしいみたいな話、「あのときバブルだったよね」というようなことが多い。
例えばアメリカでITバブルが起きている2000年、当時のアラン・グリーンスパンFRB議長が優秀なスタッフ、エコノミストを総動員して、日本の平成バブルの研究をやらせています。そこからバブルの定義ができるかと。バブルの発生から崩壊までさまざまな角度で分析して議論しましたが、株価や地価がどんどん上昇しているときに、バブルだと判定できる基準はないという結論に至りました。
ましてや株価や地価がどんどん上昇しているとき、当事者のマインドはイケイケどんどんになってしまっているわけですから、そこで一回冷静になって、「これはバブルだから」と抑えようとしても、インフレ率が低水準で安定している場合には説得力がない。というのも、金融政策は本来、株価や地価を上げたり下げたりするためにあるのではなく、あくまでもモノに対する通貨の価値、即ち物価を適正水準に維持するためにあるからです。
いわんやFRBの検討結果が示すように、「これはバブルだ」と中央銀行が判定できるかというと、それはできない。要するに「バブルだから金融を引き締めましょう」という金融政策上の判断はできないのです。
繰り返しになりますが、インフレなら「いまインフレだ」と判定できます。通常、物価がだいたい四~五%、もっと上がるかもしれないというときは、景気が過熱しているという意味でインフレだと判定できます。しかし、株価が5%上がった、さらに10%上がったらどうでしょう。これで金融引き締めをやるわけにもいきません。
例えば、アメリカの株価は新型コロナウイルス・ショックが起きた2020年3月から上昇を続け、2021年3月には50%、八月は60%アップになり、いわゆるバブル懸念が市場にも漂ったのですが、FRBは金融緩和を継続しました。というのも実体経済はコロナ禍の重圧がのしかかったままですから、実体経済を痛めつける金融引き締めに踏み切ることは誰が見ても無茶だからです。勿論、前述したようにバブルだという判定は不可能ですからなおさらです。
ともあれ、FRBは2000年以来、バブルに関してできることは何かと発想を変え、株価が急落して、それが続くと「もうバブルは崩壊した」と判断するようになりました。つまりリアルタイムで「バブルだ」という定義はしないで、逆に崩壊して初めてバブルだったということで、バブル崩壊が引き起こす金融市場全体の機能障害を最小限に食い止めて、実体経済への影響を少なくする事後政策に専念するようになったのです。