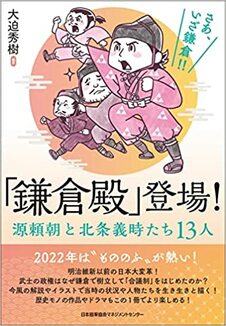「鎌倉殿の13人」の高齢者プロフィール
それでは、「鎌倉殿の13人」の顔ぶれを見ていきましょう。
生年未詳も多いですが、推定年齢順に並べると、おおよそ次の通り。
1130年代以前の生まれは、三浦義澄(27年)、足立遠元(30年代前半?)、安達盛長(35年)、北条時政(38年)、二階堂行政(30年代後半?)。
1140年代生まれは、三善康信(40年)、梶原景時(40年代?)、比企能員(40年代?)、八田知家(42年?)、中原親能(43年)、和田義盛(47年)、大江広元(48年)。
ここまで本連載で何度か登場した、おなじみの東国ボスたちが多いですね。
最年長の三浦義澄は73歳で、若い大江広元でも50歳を過ぎています。年老いて、経験を積み、物事に詳しい人のことを、「宿徳老成」といいます。略して宿老。13人は、まさに宿老の名にふさわしい高齢の役員たちでした。
18歳の頼家から見ると、「おじいちゃん」ばっかり。一歩間違うと、老人会。
いや、ひとりだけ若手が紛れ込んでいました。
1163年生まれの江間小四郎こと北条義時です。義時は、“専務取締役”北条時政の息子。このとき37歳でした。この人事は実力というより、時政がゴリ押したのでしょう。
さらにもうひとり。13人には含まれませんが、時政の娘・「御台所」政子も“相談役”のように振るまい、強い発言力をもっていました。義時を合議制メンバーにねじ込んだのは、政子だったのかもしれません。1157年生まれの政子は、このとき43歳でした。
なお、北条一族が複数人顔を出しているのに、源氏の名はありません。
この13人は、経歴・役割から大きくふたつのグループに分けられます。「先代」頼朝時代からの御家人の9人と、京都から下ってきた官人の4人です。
さらに御家人は所領をもつ国ごとに、伊豆の北条、相模の三浦・和田・梶原・安達、武蔵の比企・足立、常陸の八田に分けられます。
官人は、政所別当の大江(中原)広元、問注所執事の三善康信、そして大江の兄・中原親能と藤原南家出身の二階堂行政です。大江広元は、まだ中原姓を名乗っていました。