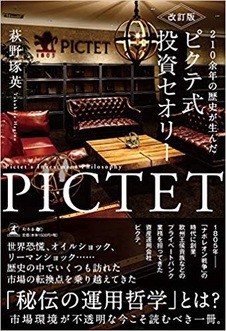「アクティブファンド特集」を見る
日本経済に壊滅的な打撃を与える、高齢化・人口減少
次は日本の人口減少を考えてみます。インフレへとつながる大きな要因である財政赤字は、日本の国力減少を引き起こす少子高齢化社会の進行と密接につながっています。
現在でさえ、日本は約1100兆円もの多額の借金を抱えているのです。単純計算では、乳幼児から高齢者まで国民一人当たり約900万円弱の借金を抱えていることになります。今日の低金利下でも、この借金の利払いは毎年約10兆円に及びます。
国の借金が膨らみ続ける原因ははっきりしています。歳出(支出)規模に見合う歳入(収入)が得られていないため、その差額を国債などの発行(借金をすること)で埋めているのです。
もちろん健全化できることが望ましいのですが、そのためには難しい問題を解決しなければなりません。それは社会保障費の増大です。2018年度予算の政府予算によると、医療などの社会保障費は一般会計ベースで税収の55%にまで達しています。
![[図表1]社会保障給付費の推移 出所:国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」、2016年度、2017年度、2018年度(予算ベース)は厚生労働省推計、2018年度の国民所得額は「平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成30年1月22日閣議決定)」 (注)図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2018年度(予算ベース)の社会保障給付費(兆円)である。](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/d/8/600/img_d8895f5473bcfaa3bd0859053938b842215146.jpg)
出所:国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」、2016年度、2017年度、2018年度(予算ベース)は厚生労働省推計、2018年度の国民所得額は「平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成30年1月22日閣議決定)」
(注)図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2018年度(予算ベース)の社会保障給付費(兆円)である。
日本は高齢化が進むことで社会保障費が伸び続ける一方、人口が減少しているので経済が停滞し税収が伸びず、結果的に税収に対する社会保障費の割合が伸び続けているのです。
今後、この状況はさらに悪化すると考えられます。人口の減少は加速化しGDPの成長を止め、次いでその規模自体を縮小させることになるでしょう。GDPは日本が生み出す付加価値の総額であり、「消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)」の式で計算します。生産年齢人口の減少は働き手が減るだけでなく、消費の主役も減ることになるので内需が縮小し、企業は国内投資を控えるようになります。「消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)」の「消費+投資」が小さくなるのですから、GDPの成長も規模も小さくなるというわけです。
資産を「守る」「増やす」「次世代に引き継ぐ」
ために必要な「学び」をご提供 >>カメハメハ倶楽部
一方、高齢者が617万人増える推計なので、その人々が消費の下支えをしてくれそうですが、実は高齢者も2045年の約3920万人をピークに減少へ向かってしまいます。
2010年と2060年の2時点の高齢者人口を比べれば増加しているように見えますが、実態は高齢者も減っていきます。現状のままでは経済成長率が低下して財政破綻や社会保障制度の行き詰まりを招き、日本経済に壊滅的な打撃を与えるという危機的な状況なのです。
1億2千万人超の人口こそ、政策でつくり出されたもの
急速な人口減社会の到来を防ぐために、多くの施策が準備されているとはいえ、今後、人口減少を止められるのかと言えば、それほど簡単なことではないというのが私の意見です。なぜなら1億2000万人を超えた現在の日本の人口は、明治維新以降の富国強兵政策の一環である「産めよ増やせよ」政策によって、人工的につくり出されたものだからです。
日本の国土に対して適切な人口は現在の半分程度、6000万~7000万人程度ではないでしょうか。この人口はイタリア(約6100万人)、イギリス(約6400万人)、フランス(約6600万人)と同水準です。これらの国々の食料自給率はカロリーベースで(平成23年・出所:農林水産省)イタリア61%、イギリス72%、フランス129%ですが、日本の数値は39%にとどまります。
![[図表2]先進各国の食料自給率 ※FAO“Food Balance Sheets”、各政府の公表値等を基に農林水産省で試算。 ※データは遡反修正されることがあります。 出所:農林水産省「食料自給表」のデータを基にピクテ投信投資顧問作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/c/a/600/img_cabedf68ddc13aee81942090dc54c02893626.jpg)
※FAO “Food Balance Sheets”、各政府の公表値等を基に農林水産省で試算。
※データは遡反修正されることがあります。
出所:農林水産省「食料自給表」のデータを基にピクテ投信投資顧問作成
耕地と牧草地の面積も、イタリア12.8万㎢、フランス28.5万㎢、イギリス16.9万㎢に対し、日本はわずか4.7万㎢に過ぎません。個人的には食料の自給率が適切な人口の決定要因と考えていますので、日本の国土で1億人以上を養えていることこそ逆に驚異的なことだと思ってしまいます。
もともと日本では、幕藩体制下で地方分権が進んで全国津々浦々まで田畑が開墾された江戸時代の末期でも、人口は3400万人程度と推計されています。その頃の人口がいわば、日本の国土で自給自足して何とか養っていける水準で、人口が多くなりすぎると産児制限として間引きや堕胎が暗然と行われていました。一方、明治政府はその両者を法律で禁じ(堕胎罪)、多産を奨励しました。帝国主義の時代、国力を反映するものとして兵力数のベースとなる人口は非常に重要な要素であったからです。
また、この時期に文明の進歩によって人口転換(Demographic Transition)が起こり、多産多死から多産少死の時代へ突入、それは戦後のベビーブーマー時代まで続きました。その後、少産少死型へと移行していったと考えられます。同時に寿命が延びて高齢化が進みました。
その結果、明治維新以降は急激に人口が増え、人口カーブは1868年の人口約3400万人を起点に急上昇しています。その後、日本の総人口は2008年に約1億2800万人まで増えたのですが、この年を頂点に減少が始まり、厚生労働省によると65年には9000万人を大きく割り込み、高齢化率は40%近い水準になると推計されています。
![[図表3]日本の人口の推移 ※期間:1820年~2060年(推計) ※推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計):出生中位~人口置換水準到達(死亡中位)推計」 出所:Global Financial Data、国立社会保障・人口問題研究所のデータを使用しピクテ投信投資顧問作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/4/a/600/img_4a2013e2ac1d1921c1f38120582dc49b40927.jpg)
※期間:1820年~2060年(推計)
※推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計):出生中位~人口置換水準到達(死亡中位)推計」
出所:Global Financial Data、国立社会保障・人口問題研究所のデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
65歳以上の老年人口は2010年から2060年までに約617万人増加するのに対し、生産活動の中心となる15歳以上65歳未満の生産年齢人口は約3310万人、15歳未満の年少人口は約729万人減少する見通しです。そのため社会保障を考えると、2010年の時点では1人の高齢者を2.8人で支えていたのが、2060年には1.3人で支えることになるのです。
萩野琢英
ピクテ投信投資顧問株式会社 代表取締役社長
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~


![[図表4]日本と各国の人口増減率の推移(年率) 期間:1960年~2050年(推計) 出所:総務省統計局、国立社会保障・人口問題研究所のデータを使用しピクテ投信投資顧問作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/6/4/600/img_6469aa92ef761e496008a86e60722bd6154354.jpg)