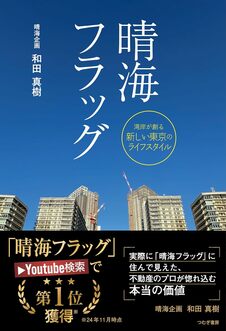ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
2040年までに開業見込みの湾岸地下鉄、「晴海駅」の可能性
「地下鉄ができれば車は必要ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、私は駅利用と車利用は競合するのではなく、むしろ共存するものだと思っています。晴海フラッグは首都高速の出入口が近く、羽田や成田への空港アクセスにも優れています。これは、すでに大きな強みと言えるでしょう。
仮に晴海駅が開業した場合でも、この地域の車利用者にとってはむしろ選択肢が広がるだけです。急な天候変化や家族の予定変更に対応するため、鉄道やバス、車を状況に応じて使い分ける環境が整うことは、非常に大きな安心感をもたらします。交通手段の多様性が地域の価値を高める鍵であり、その点で晴海地区の未来は非常に明るいと感じます。
駅がなくても十分魅力的、だが…
正直なところ、私は「駅がなくても晴海フラッグを選ぶ価値は十分にある」と考えています。実際、私自身が車通勤で晴海と銀座を行き来していますが、15~20分ほどで移動できており、不便さを感じることはほとんどありません。
それでも、湾岸地下鉄構想が実現し、晴海駅が誕生すれば街全体の価値は格段に上がるでしょう。駅の誕生は、住む人だけでなく働く人や訪れる人の流入を促し、街をより活気あるものにするはずです。そして、その結果、不動産価値にも大きな波及効果をもたらすでしょう。
私は、この未来が単なる夢物語だとは思いません。都心部の地価上昇、郊外への人口シフト、新しい交通政策の推進。これらの要素が絡み合い、「駅を中心とした街づくり」から「多様な移動手段が選べる街づくり」へのシフトを後押ししています。これまでの都市開発の常識を超えた、新しい都市モデルがここに生まれようとしているのです。
そして、この変化はすでに始まっています。次のステップでは、晴海フラッグがどのように「交通の多様性」を基盤にした街づくりを展開するのか、その詳細を掘り下げていきましょう。