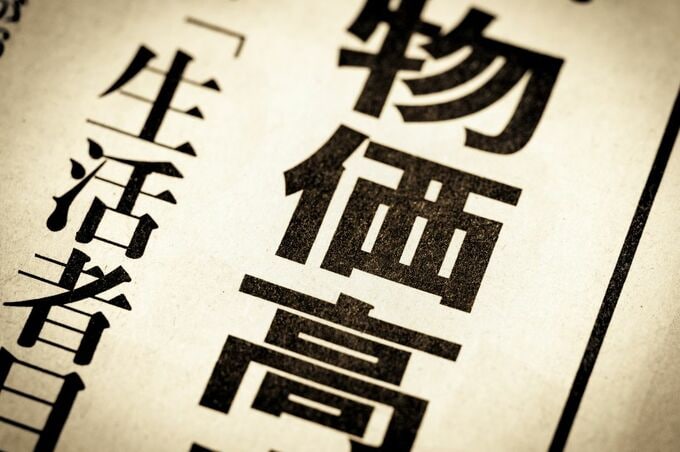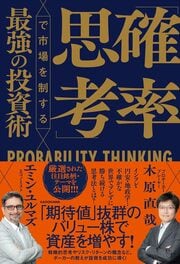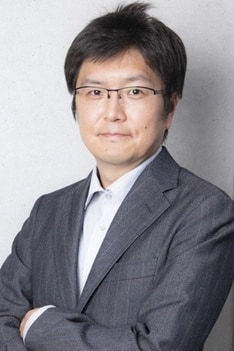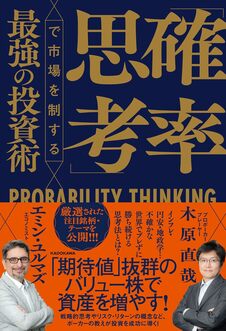インフレ下での合理的な経済行動とは
エミン:インフレにどう対抗すればいいのか、ということをよく聞かれるのですが、基本的にインフレ下ではあらゆるリスク資産が上昇します。インフレはモノの価格が上がる分お金の価値が目減りすることですが、それはとりもなおさず、お金以外の資産の価値が上昇することにつながります。
たとえば、3%のインフレ下では、株などのリスク資産は最低でも3%は上がるもので、実際はそれ以上に上昇することがほとんどです。
木原:なるほど。
エミン:これまでのように、インフレがゼロあるいはデフレの状態では、投資するインセンティブは働きません。お金をそのまま置いておいても価値は目減りしないし、デフレであればむしろ上がるので、かつてのデフレ経済下では銀行預金は正解だったわけです。
ところが、インフレ下ではお金の価値が下がるので、普段は投資しない人まで投資をするようになります。要は、お金を投資する強いインセンティブが生まれることから、株価はインフレ率以上に上昇するのです。
この現象が最もわかりやすく現れた例のひとつが、私の母国であるトルコです。2020年以降、トルコはハイパーインフレに見舞われてトルコの通貨であるトルコリラは暴落し、価値がほぼ5分の1になってしまいました。インフレ率と同じだけ株価が上がると考えれば、株価が5倍になってもおかしくありませんが、実際には10倍になっています。
なぜインフレ以上に株価が上がったかというと、トルコリラの価値がどんどん目減りしていくことで国民がパニックになり、株式投資を加速させたからです。
さすがに日本ではトルコほどの急激なインフレになることはないでしょうが、インフレ経済下では消費をするか、投資をするのが合理的な経済行動になります。
実際、これまで投資をしなかった層が危機感を持って株式投資を始めるという現象は、すでに起こっていますよね。そこに新NISAという追い風もプラスされ、これらが強力なエネルギーとなって株式市場を押し上げていくことは容易に想像できます。
木原:デフレ経済下では合理的だった預貯金も、いよいよこれからはハイリスクな行動になっていくわけですね。なにしろ預貯金だけだと、暴落中の日本円という銘柄に集中投資していることになるんですから、それはもうとんでもないリスクになりそうです。
エミン:ポーカーでは配られたハンドが弱くて降りるときでも、アンティ(最低限ベットしなければならない強制参加費)は取られるので、勝負を降りたときでも少しずつ手元のチップは減っていきます。
私に言わせれば資産を全部銀行預金にしている人たちは、まさに少しずつアンティを取られ続けているようなものです。当の本人は何も払っていないつもりでも、インフレという手数料を取られて資産の価値が少しずつ目減りしているんです。
要するに我々は望むか望まないかにかかわらず、プレーヤーにならざるを得ません。どのタイミングで、どれぐらいの頻度でプレーするかは選べるけれど、プレーするかしないかということは、もう選択の余地がなくなっているんですよ。