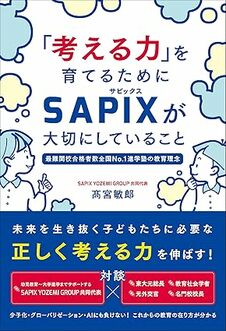対談者:北鎌倉女子学園学園長・柳沢幸雄氏

東京大学名誉教授
1947年生まれ。開成中学校・高等学校、東京大学工学部を経て、企業勤務後、同大学大学院工学系研究科化学工学専攻博士課程修了。工学博士。研究テーマは「空気汚染と健康の関係」。ハーバード大学公衆衛生大学院准教授、同併任教授を歴任。
シックハウス症候群、化学物質過敏症研究の世界的第一人者として知られ、ハーバード大学ではベストティーチャーにも選出。帰国後、東京大学大学院教授などを経て、2011年4月から2020年3月まで開成中学校・高等学校校長を務める。2020年4月から現職。主な著書に、『18歳の君へ贈る言葉』(講談社+α新書)、『男の子を伸ばす母親が10歳までにしていること』(朝日新聞出版)など。
学校には「知育」と「社会性の育成」、二つの役割があるが…
髙宮
都市部では特に、マンションの隣室に誰が住んでいるかも分かりませんし、勝手に出入りできないよう何重にもセキュリティがかかっているので、近隣住民や地域でのつながりをつくりにくい時代になっていますね。
柳沢
その通りです。そんな時代に生きる子どもにとって「社会性の育成」が叶う場は、いまや学校くらいしか残っていないということでもあるのです。
「知育」の面だけでいえば、一番教え方が上手なのは、予備校や学習塾なのかもしれません。しかし、塾で過ごす時間には限りがありますから、「社会性の育成」までは期待できません。そう考えると、生徒と教師の関係と、同年齢の生徒同士の「ヨコ」の関係、先輩と後輩の「タテ」の関係、その三つの関係性から、社会性を身につけることができる学校という場は、「社会性の育成」における絶好の環境といえるのです。
年齢や属性の異なる人たちと、どう馴染んでいき、どう存在感を出せるか。それらを体験的に学ぶことが、学校に託された大きな役割になっていると考えています。
髙宮
今や地域社会が失ってしまった役割を、学校が背負っているというわけですね。「タテ」や「ヨコ」の関係性でいうと、開成には、ボートレースの応援や部活動、運動会など「タテ」のつながりが目立つイベントや仕組みがたくさんありますね。
柳沢
それは、「タテ」の関係性の構築こそ、最良の教育法だと考えているからです。新年度における開成の教員の最大の任務は、新1年生を部活動に参加させることです。その後は、良いことも悪いことも全て先輩が教えてくれます。
教師一人では、クラスにいる数十人の面倒を見るといっても限界がありますが、その点、少し年上のロールモデルが近くにいる環境を与え、「自分もああなりたい」という先輩を見つけてさえくれれば、あとは放っておいても自然に成長するものです。
特に開成中学校は、それまで小学校で一番だった子どもたちが集まってくる学校です。そうすると、5月末の中間試験で「43人中42位」など、それまで見たことのない数字を目の当たりにすることになります。そこで意気消沈しないための仕掛けとして、部活動があり、運動会があるのです。