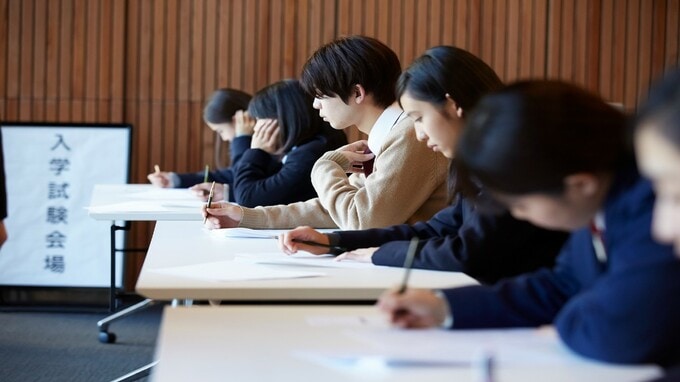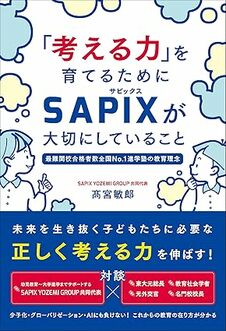ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
対談者:早稲田大学教育・総合科学学術院教授・濱中淳子氏

教育・総合科学学術院教授
1974年生まれ。東京大学教育学部卒。同大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。東京大学基礎学力研究開発センター特任研究員、リクルートワークス研究所研究員、大学入試センター研究開発部教授、東京大学高大接続研究開発センター教授を経て、2019年から現職。
教育社会学、高等教育論を専門とし、アンケートやインタビューなど社会調査を駆使した分析を行っている。著書に、『大衆化する大学一学生の多様化をどうみるか」(共著・岩波書店)、『「超」進学校 開成・灘の卒業生―その教育は仕事に活きるか』(ちくま新書)、『検証・学歴の効用』(勁草書房)などがある。
「タテの学歴」と「ヨコの学歴」
髙宮
まず、濱中先生のご専門である教育社会学では、「学歴」というものを一体どのように捉えていらっしゃるのでしょうか。そこから教えていただきたいと思っています。
偏差値が高いとされる大学や高校に入ることで、「学歴」が得られるのでしょうか。あるいは、入試における偏差値や学校の知名度などではなく、むしろ子どもたちが試験を突破するために払った努力、その努力を通して学んできたことのほうに力点が置かれるのでしょうか。
おそらく、「学歴」という言葉は、使う人によって意味合いが異なると思います。教育社会学では「学歴」という言葉をどのように捉えておられるのか。その点をご教示ください。
濱中
教育社会学では、分析をする際に、「タテの学歴」と「ヨコの学歴」という二つの「学歴」を用いています。「タテの学歴」とは大卒か短大卒か高卒かといったもので、「ヨコの学歴」は、例えば、同じ大卒であってもどこの大学を卒業したのか、旧帝大※卒なのかどうか、といったものになります。
大学進学率は今でこそかなり上昇しましたが、それでも6割ほどです。つまり、大学に進学しない/できない人も少なからずいるわけで、社会問題の観点から学歴を扱う研究者は「タテの学歴」に注目します。
他方、学歴がもたらす効果などを詳しく分析する際には、「ヨコの学歴」を用いるケースも当然にあります。
髙宮
近頃は、「入試などの試験に向けて一生懸命頑張る」という姿勢に対して、「詰め込み式の受験勉強は、むしろ子どもたちにとってマイナスだ」と疑問視する声があることは、濱中先生もご存じの通りかと思います。あるいはもっとシンプルに、「脱偏差値」を目指す、という話を聞くこともあります。
例えば、東大卒でも社会に出ると「使えない」などといった話をよく耳にします。確かに、事実としてそのような人がいることも理解しています。しかしそれは、東大に限った話ではないかもしれません。
また、これは「ヨコの学歴」を重視して採用したいと考える企業などの理屈とも重なりますが、平均的に見れば、大学入試という一つのハードルを乗り越えてきた人たち、そうした仲間との切磋琢磨の中で学んできた人たちは社会でも活躍できる力を身につけている=「使える」との考えもいまだに多くあります。
私としては、偏差値云々を語る以前に、将来を生きるうえでの基礎となる知識をしっかりと身につけること。そのためにしっかりと勉強すること。その大切さを、できるだけ誤解のないように伝えていきたいと考えているのですが、前者のような考え方、「東大卒は使えない」というような研究は存在するのでしょうか?