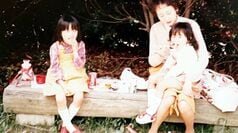「心理的瑕疵物件」は賃貸契約時に告知義務がある?
所有している賃貸物件内で人が亡くなるなどして心理的瑕疵物件となってしまった場合、次の入居者候補者に告知する義務はあるのでしょうか? 従来は、この告知義務が比較的広く解釈されており、その場で人が亡くなった物件であれば、原則として告知が必要であると捉えられてきました。
しかし、特に事件性がない死亡についてまで告知義務が生じるとなれば、高齢者の入居が賃貸物件オーナーから避けられてしまい、住まい選びの障害となってしまう問題があります。
そこで、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が、令和3年10月に国土交通省の不動産・建設経済局、不動産業課より公表されました。 このガイドラインでは、宅建業者が告知すべき死と必ずしも告知を要しない死が、次のように整理されています。
1. 自然死や日常生活での不慮の死は原則として告知不要
ガイドラインによれば、老衰や持病によるものなどいわゆる自然死については、原則として告知義務がないこととされました。
また、事故死に相当するものであったとしても、自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活のなかで生じた不慮の事故によるものも原則として告知義務がないとされています。
人が生活をする以上、これらの死は日常生活のなかで当然に予想されるものであり、さほど特別の事情によるものではないと考えられるためです。
2. 特殊清掃が行われた場合は3年間告知義務あり
たとえ自然死や日常生活による不慮の死であったとしても、特殊清掃などの対象となった場合には、死の発覚後おおむね3年間は告知義務があるとされています。 特殊清掃とは、死亡から長期間発見されなかったなどの理由から汚れが床や壁に付着していたり、害虫が発生していたりする部屋に必要となる特別な清掃です。
3. 自然死や日常生活での不慮の死以外の死は3年間告知義務あり
自殺による死や事件による死など、自然死や日常生活での不慮の死以外の死亡があった場合には、その後3年間は告知義務があるとされています。 これらの死は、その物件で今後生活することとなる入居者にとって、入居を決めるかどうかの大きな判断材料となる可能性が高いためです。
これらの死であっても、死亡からおおむね3年間を経過したあとは告知義務がありません。 ただし、事件性や周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案については3年という期間のみで区切るのではなく、個別事案に応じた判断や対応が必要です。
4. 隣接住戸などでの死は原則として告知不要
たとえ特殊清掃が行われた死や事件性のある死であったとしても、賃貸の対象となる住戸そのものではなく隣接住戸で起きたものである場合や、入居者が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で起きたものである場合には、原則として告知義務はありません。
ただし、事件性や周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案については、個別事案に応じた判断や対応が必要とされます。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資