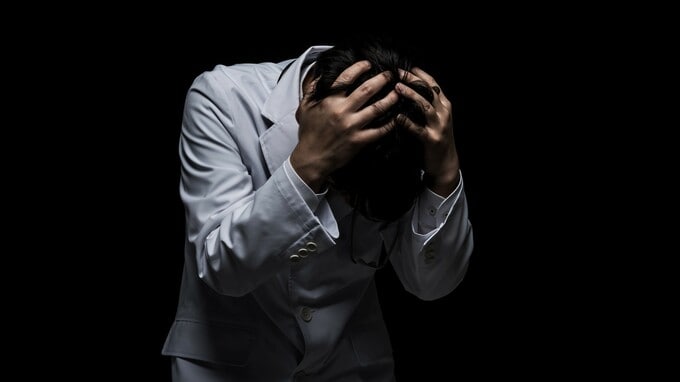患者の大病院志向が中小規模の病院を赤字にする
患者は常に良い病院、良い先生を探し求めています。
患者が重視しているのは、安心して自分の体を診てもらえるかという点です。ただ、安心の基準はその病院の専門性のような実力よりも、かかっている患者の多さや病院の知名度によるところが大いにあるといえるでしょう。自宅に近い小さな診療所より、地域で目を引く大病院(中核病院)のほうが「なんとなく安心」という気持ちが患者にあるからです。
医療機関の間には連携があって、診療所で診察を受けた際に必要ならば大きな病院へ紹介してもらうことは可能という仕組みは知っていながら、患者には「良い病院=大きな病院で診てほしい」という心理が働いているわけです。
診療所などからの紹介状なしに200床以上の中核病院を受診すると、特定療養費という費用が診察費に上乗せされます。特定療養費の金額設定は各医療機関によって異なりますが、一般的には1,000~5,000円の間で設定されていることがほとんどです。
これは地元のクリニックでも済むケースなのにわざわざ大きな病院を患者が好むことで、医療資源が無駄遣いされるのを防ぐ仕組みです。それなのに、特定療養費を負担してでも中核病院を受診して安心を取りたいという人はあとを絶ちません。
とはいえ、診療所でも十分な治療を受けることはもちろん可能です。患者の足が向かないのは、単純に情報不足にあることがほとんどです。
こうした地域で開業している医師をまず訪ね、その診療所で医療が完結しない場合は紹介状を受けて中核病院へ行ってもらうことが、地域医療構想から見る理想のサイクルです。
しかし、残念ながら患者がもつ大病院志向や病院自体のネームバリューの差から、このサイクルはうまく回っていない現状があります。
大きな病院の待合室で長時間待つことは、患者にとってマイナス要素でしかありません。しかし、混んでいることこそ、この病院が多くの患者に選ばれていることの表れだと、かえって安心感を強める患者も一定数います。
仕事帰りや休日に受診できるかといった利便性に、安心できるかどうかという判断基準が加わった結果、中核病院に患者が押し寄せ何時間も待たされるほどの混雑が発生している現状があるのです。
こうなると、200床以下の病院にとっては本来、預かるべき患者を診ることができず、果たすべき役割を果たせないまま、施設としての能力を維持し続けなければならないという葛藤が生じます。
ある程度の人材を確保、維持しつつ、その人材をフル活用できないまま固定費を垂れ流さざるを得なくなり、赤字の常態化を招いてしまうのです。
山本 篤憲
株式会社アリオンシステム
代表取締役社長
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】