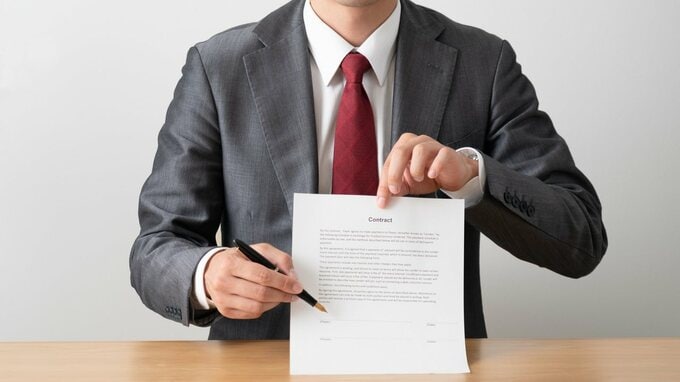あなたにオススメのセミナー
【関連記事】フェラーリは経費…うるさい税務調査官を黙らせた、意外な一言
短期借入金は、利息を払っている限り実質「無期限」
銀行などの金融機関の融資は、返済期間が長いほうがいい。返済が長ければ長く借りられる。1回あたりの元金返済も少なくなり、総じて資金繰りが楽になる。
では、短期の借入はダメなのかというと、そんなことはない。むしろ短期の借入は究極の長期借入金になり、長期的に資金繰りを良くする。
どういうことか。1年後に一括返済する条件の短期借入金は、借入期間中の元金返済がなく、利息だけ払う。長期の借入が毎回の返済に元金を含めながらコツコツ返済していくのに対し、短期借入は元金返済を繰り延べるため、手元の資金もほとんど減らない。
100万円借りたら、多少の利息は払うが、100万円をほぼ丸ごと1年間にわたって手元に置いておくことができる。
しかも、借り手が望めばほとんどの場合、借入契約は延長可能。利息をきちんと払っていることが大前提だが、返済期限が近づくと銀行などの金融機関から延長の申し出がある。
「はい、延長でお願いします」
そう答えるだけで、もう1年借りることができる。
翌年も同様の流れで、さらに1年借りることができ、その翌年も同様に借りることができ、といった具合に、ずっと借りることができ、手元に現金を確保できる。言い方を変えれば、利息を払っている限り、短期借入金は無期限の借入金であるということ。
貸し手である銀行などの金融機関としては、延長してもらうことで利息が取れる。「期限が来たので返済してください」と返済を迫る合理的な理由がない。
借り手である会社にとっても、利息を払うだけで手元の資金が増えるため、完済する理由はなく、借りっぱなしで良いのだ! この手法を短期継続融資というが、金融庁も推奨している融資なのでぜひ活用してほしい。
融資の「据置期間」は交渉の余地アリ
融資を受ける際、必ず交渉したいのが据置期間。据置とは、融資実行から何年間かは元本を返済しなくてもいい(利息は払う)というもので、据置期間が長いほど現金を手元に置いておける期間も長くなる。
資金繰り経営とは繰り延べ経営。現金の出は遅ければ遅いほど資金繰りが楽になる。
注目したいのは、ほとんどの融資の据置期間は「最長何年」という書き方をしていること。最長の話なので、「最長5年」と書かれていても、必ず5年間は元本返済がないわけではない。
むしろ、最長の期間を確保できるのは珍しい。たいていの場合、最長5年なら「3年据置」「1年据置」という話になる。
業種や業界によって据置期間が決まっていることもあり、私たち税理士業界は「最長5年」と書いてある融資でも、ほぼ毎回「1年です」と言われてしまう。それに対して「そういうもんか…」と思う人が多い。
しかし、ここで諦めてはいけない。交渉する。先日、コロナ関連融資で資金調達した時の話。申し込みの電話をしたところ、担当者は案の定「1年」と言う。「先生の業種で5年は無理です」と言われた。
ここで交渉。
「5年でお願いします」
「それは無理です。先生の業種は仕入れもないわけですし」
そんなことは分かっている。でも、粘る(笑)。
「そこをどうにか、5年でお願いします」
「無理です」
どうやら5年は無理そうなので、ここで作戦変更。こっちも多少、妥協する。
「では、何年ならいけますか」
「そうですねえ、頑張っても2年ですねえ」
1年が2年になった。でも、まだ粘る。
「2年ですか。2年はつらいです。コロナがこの先どうなるか分からないので、3年でお願いします」
「いや、そもそも1年ですから、3年は無理です」
「どうにか3年でお願いします」
そう言って、私は電話を切った。
結果、どうなったか。後日、郵送で書類が届き、そこには「据置期間3年」と書いてあった(笑)。つまり、原則1年でも交渉次第では3年にできるかもしれないということ。諦めたら1年だが、頑張った結果3年。
2年の差は大きいよね。金融機関によるが、原則1年の据置期間から、2年、3年への変更を担当者が判断しているケースが多い。
もちろん、審査や決算書の確認があるため、信用格付を高くしたり、決算書の見栄えを良くしたりしておくことも大事だが、まずは交渉だ。交渉はタダだから。資金繰り経営を実現していくために手間と労力を惜しんではいけないのだ!
菅原 由一
SMGグループ CEO
SMG菅原経営株式会社 代表取締役
SMG税理士事務所 代表税理士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】