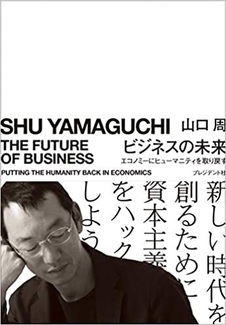【Jグランドの人気WEBセミナー】
税理士登壇!不動産投資による相続税対策のポイントとは?
<フルローン可>「新築マンション」×「相続税圧縮」を徹底解説
新卒一括採用というシステムが続く本当の理由
ここに大きな問題があります。というのも、評価には必ず「精度と時間のトレードオフ」が発生するからです。短期間に評価しようとすればどうしても精度が犠牲になり、精度を高めようとすればどうしても時間がかかる。特に「個性」や「創造性」といったパーソナリティに関わる要件は、ペーパーテストで評価することができないため、高い精度でこれを評価しようとすれば膨大な時間とコストがかかることになります。
図は人材育成の世界でよく用いられる典型的な「氷山モデル」を図示しています。なぜこれが「氷山」のメタファーで表現されるかというと、人材要件は「水面上に出ていて外側から観察しやすい要件」と「水面下に沈んでいて外側からは観察しにくい要件」の組み合わせになっているからです。
受験勉強で試されるような問題解決の能力はいうまでもなく「知識」と「スキル」に該当し、これは相対的に外部から評価しやすいため、新卒一括採用においても評価が可能でしょう。
一方で、個性や創造性というのはコンピテンシーや動機・パーソナリティに関わる項目ですから、短期間に外部から評価するのは非常に難しい。コンピテンシーのことを能力やスキルと混同している人がよくいますが、両者はまったく異なる概念であることに注意が必要です。
コンピテンシーという概念を最初に提唱したのはハーバード大学で行動心理学を教えていたデイヴィッド・マクレランドですが、彼がなぜこのような概念の導入を提唱したかというと、親の学歴や収入に大きく影響されてしまう知識やスキルで人材を評価すると社会の格差を拡大再生産してしまうという問題意識があったからです。
これは現在でも同じですよね。高額の塾の費用を負担できる家で育った子供とそのような環境にたまたま恵まれなかった子供では「知識」と「スキル」に差が生まれてしまうのは当然に想定できることです。したがってこのような項目に頼って選抜を行っている企業の採用担当者は、社会の不公正を拡大再生産するエンジンをまさに担っているということですが、このような自覚が当事者にあるのでしょうか。
■革命もまた「いまここにいる私」から始まる
話をもとに戻せば、マクレランドはこのような不公平の影響を表白するためにコンピテンシー、すなわち「ある局面に向き合った時、どのようにしてその問題を処理しようとするか」という思考特性・行動特性を測ることで人材を選抜することを唱えたわけです。
現在では、特に海外の企業ではインターンを通じた採用が一般的になっていますが、なぜインターン形式が主流になっているかというと、実際の仕事ぶりを観察してみないとコンピテンシーやパーソナリティはよくわからないからです。
以上のようなことをつらつらと考えれば考えるほど、結論は一つしかないということになります。それは「誰も個性ある人材、創造性溢れる人材など、本気では望んでいない」ということです。もし本気で望んでいるのであれば、矢も盾もたまらず、このような採用方式は撤廃されているはずだからです。
システム思考の立脚点となるアンカーポイントは「現在のシステムは、現在の結果を生み出すために完璧に最適化されている」という現状認識です。本書をここまで読んだ読者の方なら、まず間違いなく現在の教育システムに大きな問題があるとお考えでしょうから、「現在の教育システムは完璧に最適化されている」という指摘に強い違和感を覚えると思います。
しかし私は、これまでに、多くの複雑な問題に関わった経験から、このように指摘しています。というのも、このような複雑な問題を解くためにシステムを分析すると、多くの場合、人々が実現しているのは、彼らがタテマエとして口にしている「望ましい未来」ではなく、彼らがホンネとして「いま望んでいること」そのものであることがほとんどだからです。
これはつまり、私たち全員が、現在の教育システムから少なからず見返りを受け取っており、その見返りが、システムを変えることで失われることを望んでいない、ということを意味します。端的に言えば、現在の教育システムを生み出しているのは、いまこの本を読んでいるあなた自身だということです。この認識を真ん中におかず、文科省が悪い、教育現場が悪い、塾が諸悪の根源だと声を荒げたところで、今日の問題が解決することは永遠にありません。
いま現在の世界の悲惨さを生み出しているのは、当の自分自身であるという意識は、筆者が示したすべての改革案の根っことなるものだと思います。
「どこかにいる誰か」によって問題が起こされている以上、それを修正するのもまた「どこかにいる誰か」だと考える人で世の中は溢れかえっています。そのような人々による憎悪に満ちた攻撃の言葉は、仮想空間をゴミ捨て場のようにしてしまいました。しかし、このような世界認識の末には「停滞の暗い谷間」しかやってこないでしょう。
もし私たちが「成熟の明るい高原」のような社会を作りたいのであれば、まず必要になるのは、「いまここにいる私」によって問題の多くが引き起こされている以上、革命もまた「いまここにいる私」から始められなければならないという意識をもつことでしょう。
山口周
ライプニッツ 代表
↓コチラも読まれています
ハーバード大学が運用で大成功!「オルタナティブ投資」は何が凄いのか
富裕層向け「J-ARC」新築RC造マンションが高い資産価値を維持する理由