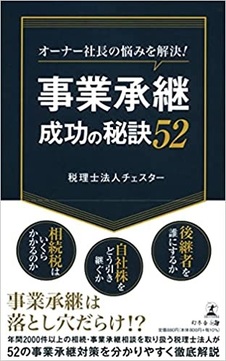配当を出している場合、配当金額を見直す
類似業種比準方式は、「配当金額、利益金額、純資産価額」の3つの「比準要素」を、類似業種の上場企業のそれらと比較し、計数操作を加えて株価を算出します。つまり、比準要素のうちの1つまたは複数の変動が株価に影響を与えます。
しかし、3つの比準要素のうち、利益金額と純資産価額は、費用や現金支出が多くなれば、結果として下がることはありますが、会社が完全に自由にコントロールできるものではありません。
一方、配当金額は、会社法上認められる分配可能額の範囲内であれば、引き上げも引き下げも、会社が自由にコントロールできます。そのため、類似業種比準方式が適用される会社で現在は配当金を出している場合、利益などの対策とあわせて、配当金を見直すことは、自社株評価に影響を与える検討項目になります。
配当金を見直す際のポイントは以下の点です。
まず、類似業種比準方式において、計算に用いる配当金額は、原則として前期と前々期の配当金額を平均したものとなります。そこで、例えばこれまで配当を出していた会社で、次年度と次々年度の配当金を引き下げれば、結果として株価が下がる影響があります。2期の平均を取るので、次年分だけ引き下げれば効果は半分となります。
ただし、親族のなかに、生活資金として配当金をあてにしている株主がいるような場合、配当を引き下げるのであれば、株主に対して大きな影響を与えることを理解しておく必要があります。なお、記念配当や特別配当などの臨時的な配当は、ここでいう「配当金額」の範囲には入りません。
なお、類似業種比準方式で株価が計算される際に留意すべきこととして、3つの比準要素のうち2つがゼロだと「比準要素数1の会社」という分類になり、さらに3つ比準要素がすべてゼロだと、「比準要素数0の会社」という分類になり、原則として、純資産価額100%での計算となります。多くの場合、純資産価額のほうが株価は高くなるので、できればこれらに該当するのは避けたいところです。
例えば、もし株式の移転を予定している年度の直前3期の業績が赤字で利益がゼロだとすると、配当金もゼロであれば、「比準要素数1の会社」となります。すると、かえって株価が上がってしまう可能性があります。この点は十分に注意してください。
税理士法人 チェスター
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】