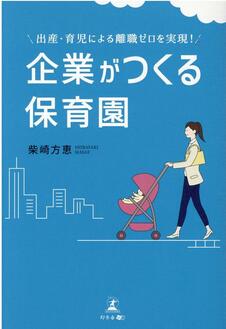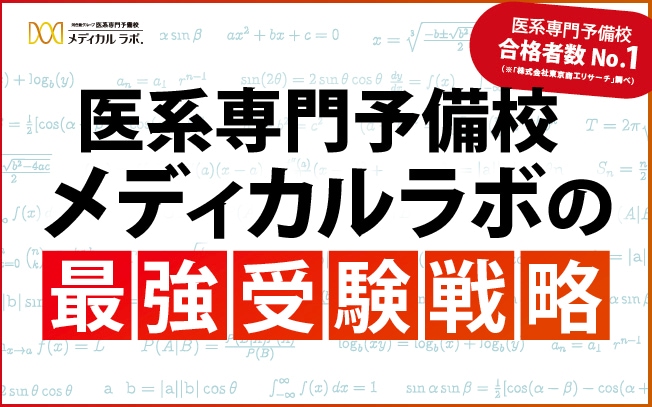育児しながらの勤務で「職場の人間関係のひずみ」が…
子育て中のお母さんたちの悩みのなかでも、特に多いのが職場の人間関係に関するものです。
働くお母さんたちと接していると「今の職場の人間関係に疲れてしまい、転職しようかと思っている」という相談を受けることも少なくありません。
子育てをしながら働いていると、周囲のサポートを必要とする場面が何度もあります。同僚にも子どもがいて、子育ての事情を実感をもって分かり合える同士であればまだよいのですが、そうでない場合は、頼る側も頼られる側も徐々にストレスが蓄積していきます。
例えば、子どもを預けて働きだしたときに、お母さんたちの大きな負担になることの一つに、子どもの突然の体調不良があります。朝は元気に登園したのに、保育園から発熱の連絡が来て慌てて迎えに行かなければならないというのはよくあることです。
特に、保育園に通いだした頃は感染症にかかりやすく、頻繁に熱を出すケースもあります。そのたびに、仕事の都合をつけて迎えに行かなければならないのは、物理的にも精神的にも大変です。場合によっては、同僚に仕事を引き受けてもらわなければならないこともあるでしょう。
最初は、頼られる側も、快く仕事を引き受けてくれていたとしても、それが度重なると、負担に感じるのも仕方のないことかもしれません。頼む側としても負担をかけることは分かっているので、仕事を頼むときにストレスを感じ、自分で抱え込んでしまうというケースもあります。
短時間勤務のために残業ができず、溢れた分の仕事を同僚に頼むこともできず、仕方なく持ち帰って、子どもを寝かしつけたあとに仕事をするという人もいます。

「女性が多いから育児に理解がある」わけではない
女性が多い職場だから育児に理解があるとも限りません。子育てに主体的に関わった経験のある人が少ない職場では、子育てをしながら働く大変さを、なかなか理解されにくい傾向があります。
多少、仕事が大変であっても、職場の人間関係が良好であれば乗り切れるものです。しかし、職場に居心地の悪さを感じ、わが子には保育園に長時間預けていることを後ろめたく思い、仕事と育児が両立できない自分を歯がゆく思う――。
そんなふうに幾重にもつらさを抱えて働いている場合、「ここまでして働かなければならないのだろうか」という気持ちになるのも仕方のないことです。
「マミー・トラック」によってキャリアを絶たれる
それでは、育児をしながら働く女性に対して、配慮の行き届いた会社なら長く働けるのでしょうか。実はそうであるとも限りません。過剰な配慮によって、キャリアアップの機会を奪われ、仕事へのモチベーションが下がってしまうというケースもあります。
「マミー・トラック」という言葉があります。仕事と育児の両立ができる働き方であるものの、昇進・昇格の道が閉ざされたキャリアコースを指す言葉です。この言葉は1980年代にアメリカで生まれました。
当時のアメリカは、子育てしながら働く女性が急増していたにもかかわらず、保育の環境が十分に整っていないという段階にありました。そのため、この言葉を提唱したフェリス・シュワルツは、女性の働き方を、仕事を優先するのか、仕事と家庭を両立させることを優先するのかの二つに分けて考えたのです。