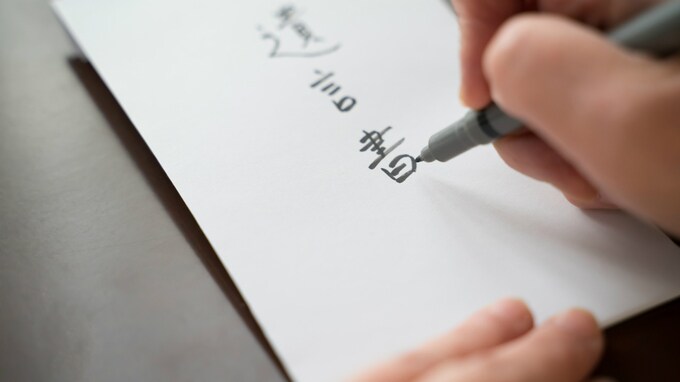遺言能力の判断で重要なのは「医師等による診断結果」
では、どのような場合に「公正証書遺言」が無効とされているのでしょうか。
遺言能力の判断にあたっては
・遺言者の年齢
・当時の病状
・遺言してから死亡するまでの間隔
・遺言の内容の複雑さ(本人に理解できた内容であったか)
・遺言者と遺言によって贈与を受ける者との関係
等が考慮されます。
上記の要素を判断するに際に一番重要なのは、遺言を書いた当時の「医師等による診断結果」です。
公正証書遺言が無効と判断された裁判事例
公正証書遺言が無効とされたケースとして、東京地方裁判所平成11年9月16日判決の事例があります。
このケースは、知的能力が低下し、便所と廊下を間違えて廊下を汚してしまうような状態だった75歳の男性が、「高度の脱水症状、腰椎骨折、パーキンソン病」と診断されて入院。入院後間もなくその妻と、懇意にしていた税理士が主導して公正証書遺言を作成したというものです。
この事例では、病院まで公証人が赴いて遺言を作成しました。その際、公証人が遺言内容を読み聞かせましたが、遺言者はこれに対して一言も明瞭な返答ができませんでした。当然具体的な遺言ではなく、「ハー」とか「ハイ」とかいう、単なる音を発していただけだといいます。
そのため、公証人が担当医師に『遺言能力がある旨の診断書を交付してほしい』と求めたものの、医師は首を縦には振りませんでした。「遺言者は通常の生活における一応の理解力、判断力はあるが、遺言能力ありとの診断書は書けない」として断ったそうです。
公証人も『これは、遺言能力の有無の判断が難しいケースだ』という所感は抱きました。しかし、それでもなお遺言者とのやりとりから遺言能力があると考えて、遺言を作成します。
しかし、遺言を書いた約3週間後には、その男性は「パーキンソン病により痴呆が進行し、中枢性失語症による言語機能の喪失、精神状態については障害が高度で常に監視介助または個室隔離が必要」という症状が固定してしまいました。
裁判所は上記の事情を総合的に考慮し、遺言者には「遺言能力がなかった」として公正証書遺言の効力を否定しています。