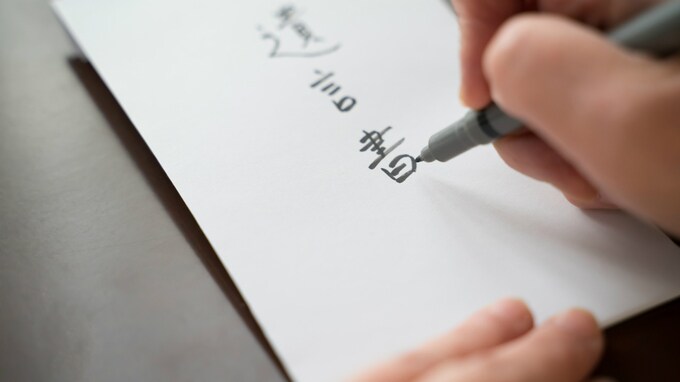理由のひとつとして、『遺言の作成は妻や税理士が主導していて、当の本人は遺言を書く意思を周囲に示していなかった』という点をあげました。
以上の裁判例を踏まえると、認知症等の症状により判断能力が疑われる人の遺言を作成する場合には、遺言の作成前(とできれば後にも)医師の診断書(特に遺言能力に問題ない旨の記載)を得ておくことが必須であると言えます。これは公正証書遺言であっても同様です。
また、遺言の効力を争う側からしても、遺言作成当時の状態がわかる医療記録・介護記録などの証拠の収集が非常に重要となります。
具体的にどのような証拠が必要なのか。またその収集方法については、弁護士と相談しながら進めることが適切です。弁護士には、そういったプロセスを効率的に進めるノウハウがあります。
また、遺言作成から長期間経過している場合には、医療機関での記録が廃棄されてしまう可能性もあります。そのため、早急に証拠収集を進める必要があります。
※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。
北村 亮典
こすぎ法律事務所弁護士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】