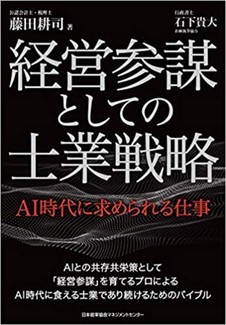新たな技術の登場によって人間が不要になる
業務の低価格化による間接的技術的失業
私は技術的失業を、「直接的技術的失業」と「間接的技術的失業」に分けて考えています。
直接的技術的失業とは、先述した自動改札や製造ロボットのように、新たな技術の登場によって人間が不要になるものです。一般的な「技術的失業」は、これを指します。
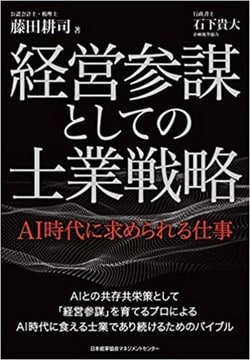
その一方で、「間接的技術的失業」とは、技術革新により業務の低価格化が進むことで、利益が出なくなり、ビジネスモデルが成り立たなくなるものです。この「間接的技術的失業」はじわりじわりと進行するので、ある時点で明確に認識できるものではありません。
パソコンやスマートフォンをはじめとするIT製品の進歩により、一人当たりの生産性は大幅に上がり、こなせる作業量も大幅に増えました。IT化以前は、書面の連絡は郵便などで配達する必要がありましたが、現在はパソコンで電子メールを書き、送信ボタンをクリックすれば何百人、何千人に対する一斉送信も可能です。何かを調べたければ手元のスマートフォンで検索すれば、その場で膨大な情報が即座に入手できます。
会計事務所を例にすれば、かつては手書きで会計帳簿を作り、その都度、電卓を使って計算が合うかを確認し、合わなければその原因を調べて訂正していました。決算書も当然手書きです。ところが、今は会計システムに仕訳を入力するだけで自動的に会計帳簿も決算書も作成できます。合計額がずれることもありません。
このように、一人の人間がこなせる業務量は、技術の進歩によって数倍、数十倍に上がり、業務の正確性も大幅に上がっています。ところが、これに伴い給料も数倍、数十倍に上がったかというと、決してそうではありません。人件費は変わらずに、こなせる業務量が上がると、1件あたりの業務に係る人件費は大幅に下がります。こうして低コスト化に成功した企業は売価を下げても利益が出るため、売価を下げてより多くの顧客を獲得していきます。このようにして業界の相場の低下をもたらす流れができていきます。
情報格差の解消が間接的技術的失業を後押しする
加えて、インターネットによる情報格差の解消が間接的技術的失業を後押しします。
インターネットの普及以前は、士業を探すのは知人による紹介が主流でした。依頼者はその士業が提示した料金が高額と感じても、より安くやってくれる士業を知らなければ、目の前の士業に依頼するしかありませんでした。こうした情報格差のおかげで多くの事務所は高い料金を得ることができていました。