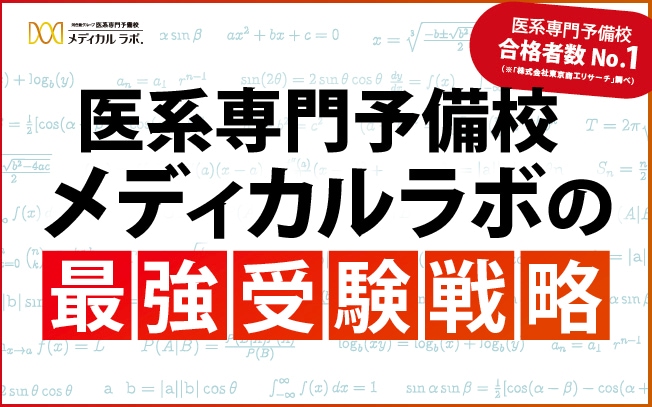様々な分野における「発達障害」の定義
「発達障害」を理解するために必要なのは、教育的な側面からのとらえ方だけではありません。法律や医療分野における定義についても知っておく必要があります。
法律での定義
平成16(2004)年に制定された『発達障害者支援法』で、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令に定めるものをいう」と規定しました。
用語に重複がみられますが、これまで見過ごされてきた発達障害に対して、一刻も早い支援施策が求められていたため関係者の努力が結実し議員立法されたものです。平成17(2005)年に『発達障害者施行令』(政令)では、発達障害を「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする」としています。
医療での定義
みちのく療育園(医療型障害児入所施設)の施設長で医師の伊東宗行氏によれば、基本的に医学では昭和46(1971)年に愛知県心身障害者コロニー(現・医療療育総合センター)が設立されたときに発達障害を「遺伝的、周産期、その後の環境の影響などによって脳障害を受けた精神遅滞や脳性麻痺等の心身障害」と規定されたといいます。医療の立場であると、発達に何らかの障害をもたらす病気は、すべて発達障害と考えるのかもしれません。
さらに、精神疾患を診断するマニュアルというものがあります。WHOが作成しているICD‐10(国際疾病分類)とアメリカ精神医学会(APA)が作成しているDSM‐5(精神疾患の診断・統計マニュアル‐5版)が主です。10と5の数字は改訂された数を表します。
これらの診断基準に基づいて医師の診察のもと、自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)などの診断名がつきます。
子どもの場合、発達障害の診断があり、それをもとにして福祉の行政機関である児童相談所から「療育手帳」を発行されることになります。この「療育手帳」が取得されることによって、日本では障害福祉サービスを受けることができるようになります。

【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】