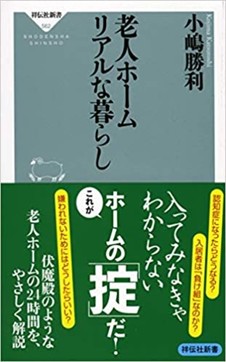職員の数だけ「流派」は存在する理由
茶道や華道、日舞の例を出すまでもなく、一見、同じように見えても日本文化の中のそれぞれの流派には流派ごとのこだわりやルール、作法などが存在していることは、誰もが知っていることでしょう。あなたが老人ホームに入居を検討しているのであれば、事前に老人ホームの「流派」を確認しなければならないかもしれません。
老人ホームに「流派」? そう、老人ホームにも「流派」があるのです。
老人ホームの「流派」は、いったいどのようにして決まるのでしょうか? 教科書通りの言い方をすれば、老人ホームの「流派」は、会社の介護方針、介護理念などをベースにして決まっていきます。しかし、実際には、老人ホームのホーム長(管理責任者)の考える「流派」が、そのままホームの介護スタイルになっていくのが現実でしょう。

さらに話をややこしくしているのは、多くのホームで、ホーム長などの管理者がホーム内を正しく仕切れていない、という事実です。
老人ホーム内の統治と一言でいっても“言うは易し行なうは難し”であり、ホーム長がしっかりと統治をするのはそうそう簡単ではありません。それゆえ、中には介護方針は介護現場に任せ、ホーム長は運営(収益管理)に特化しているホームもあります。
ホーム長が介護現場に口を挟まないこのようなケースでは、ホームの「流派」は看護師や介護主任の考え方に左右されていきます。ホーム長による統治が上手くいっていない老人ホームには、複数の「流派」が存在し、「流派」同士で権力争いが生じています。
「流派」同士の権力争いと書くと、政治家の派閥争いのようなイメージを持ってしまう読者もいるでしょうが、老人ホームでの権力争いとは、自分たちの「流派」で介護サービスを提供したい、ということにほかなりません。まじめに介護に取り組んでいる多くの介護職員には、介護に対する思いや考え、こだわりがあります。そして彼らの多くは、介護業界に入って最初に師事した先輩の「流派」を引き継いでいるのです。
現在の老人ホームの職員は、そのほとんどが既存の介護事業所からの転職組なので、極端なことを言えば、職員の数だけ「流派」が存在しています。
経営者なり、ホーム長なり、介護主任なりのリーダーシップが発揮されているホームは、一定のガバナンスが存在し、統一された介護サービスを提供することができます。しかしそうでない場合、職員ごとにやり方が違い、そのたびに違和感を持っている入居者や家族は多いはずです。なかでも一番違和感を持っているのは介護職員であることは言うまでもありません。