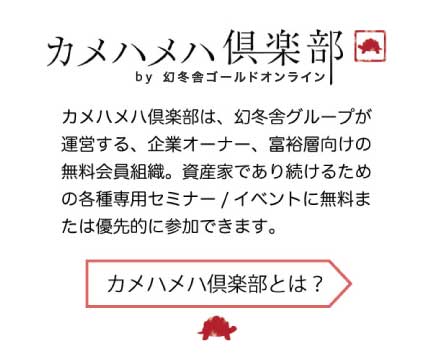「全員、親戚なんです」…静かな住宅地で告げられた言葉
「初めてご近所さんに挨拶したとき、『皆さん親戚なんですよ』って言われたんです。まさかとは思いましたが、本当に町内会の8割が親戚でした」
そう語るのは、都内で働いていた佐伯昭彦さん(仮名・58歳)と妻の美佳さん(仮名・56歳)。2人は都内のマンションを売却し、郊外の山間にある中古の一戸建てを購入。定年後を見据えた「自然豊かで人付き合いも温かそうな土地で、静かに暮らしたい」という想いからの決断でした。
購入した物件は、田園風景に囲まれた20戸ほどの集落の一角。引っ越し初日、近隣に挨拶回りをしたところ、ある家の女性から思いがけないひと言をかけられます。
「ここにいるのはみんな“XXX家”の親族だから、なにか困ったら長老に相談するといいわよ」
長老? 親族? 聞けば、昭和の初期から代々同じ一族が土地を守ってきた集落で、親戚同士が敷地を分け合いながら暮らしてきたとのこと。つまり、自分たち以外は全員“親戚付き合い”の延長線上にあるご近所だったのです。
最初のうちは、「みんなで畑の収穫祭をやるんですよ」「お正月には全戸で神社に集まるんです」といった慣習を、地域特有の“温かさ”と感じていた佐伯さん夫妻。しかし、次第にその距離感に違和感を覚えるようになりました。
たとえば、回覧板には毎月のように「XXX家のXXXさんの納骨式」や「親戚の集まりへの差し入れ募集」の連絡。ゴミ出しの場所で顔を合わせれば、「あのときの手土産、あれは親族内で非常識だって話になってたよ」といった“内輪の基準”を押し付けられることも。
「誰も悪気があるわけじゃないんです。ただ、親戚付き合いの文化がそのまま“地域のルール”として浸透していて、そこに入っていくには覚悟がいりました」(美佳さん)